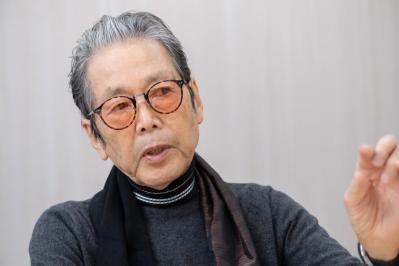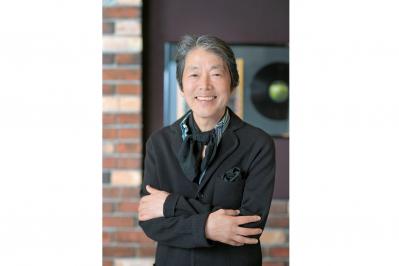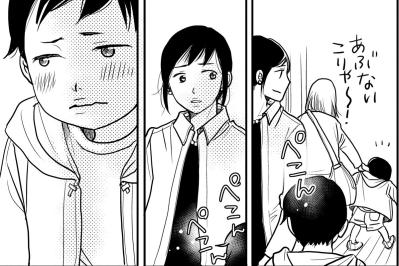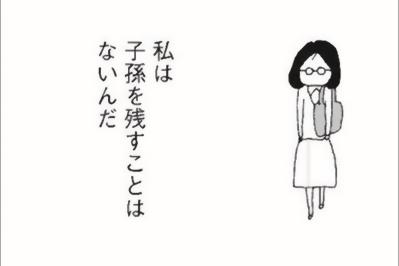【超要約】名作のあらすじを読もう!
尾崎放哉の『尾崎放哉選句集』あらすじ紹介。短歌の革新者の「せきをしてもひとり」その境地とは?
公開日
更新日
ゆうゆうtime編集部
自由律俳句の巨匠、尾崎放哉(おざきほうさい)の魅力が詰まった句集をご紹介。孤独と自然に深く結びついた彼の感性が垣間見える珠玉の句は、読む者に深い共感と静かな感動を与えます。
▼他の要約小説も読む▼
>>【超要約】名作のあらすじを読もう! 小説特集青春期から大学時代—放哉の句作の始まり
尾崎放哉は鳥取県に生まれ、青年期から俳句に親しみました。「きれ凧の糸かかりけり梅の枝」などの句は、中学時代の瑞々しい視点を反映。一高・大学時代には荻原井泉水との交流が始まり、彼の基礎俳句がより成熟していきました。この時期の句には、「一斉に海に吹かるる芒かな」といった情景描写が特徴的です。
自由な句作の確立—須磨寺時代
兵庫県須磨寺の堂守として働き出した放哉は、本格的に自由律俳句の魅力を追求します。孤独な日々の中で生まれた「せきをしてもひとり」といった句は、彼の孤独な心情と鋭い観察眼が反映されています。また、「沈黙の池に亀一つ浮き上る」など、繊細な自然描写も得意としました。
晩年の集大成—小豆島での最後の句作
小豆島での生活は、放哉の句作の最盛期となりました。ここに至るまでの彼の人生経験が豊かに投影され、「入れものが無い両手で受ける」といった屈指の名句が生まれました。この句は、彼独自の感性と無常観を物語っています。病と戦いながらも、鮮やかな自然描写と濃厚な人生観を句に込めました。
まとめ
尾崎放哉はその独特な自由律俳句スタイルを通じて、孤独と自然、人間の本質を詩情豊かに描きました。特に晩年の小豆島時代に見られる句は、彼の内面世界の真髄が詰まっています。「せきをしてもひとり」「入れものが無い両手で受ける」など、現代でも共感を呼び起こす名句が多く収録されたこの句集は、自由律俳句を理解するための必読書です。実直で力強いがどこか儚い放哉の句に触れることで、私たちが普段見落としがちな「日常の中の詩情」を発見するでしょう。
▼この小説の本編を読む▼
▼あわせて読みたい▼
>>夏目漱石の『私の個人主義』あらすじ紹介。自らの生涯と迷いを語った物語 >>太宰治の『富嶽百景』あらすじ紹介。『富嶽百景』太宰治が描く富士山と人間模様の魅力 >>樋口一葉の『たけくらべ』あらすじ紹介。樋口一葉が描く青春の葛藤と純情 - 小説『たけくらべ』の魅力※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。











![【ザ・タイガース】旋風のその先に。別れの裏にあった、知られざる物語[79歳・瞳みのるさんのターニングポイント#2]](/images/articles/thumb20260115vs9fse202645835985.jpg)