【要約小説】名作のあらすじを読もう!
柳宗悦の『京都の朝市』あらすじ紹介。「民芸」という言葉の誕生はここにあり!掘り出し物の宝庫を巡る旅
公開日
更新日
ゆうゆうtime編集部
柳宗悦が描く『京都の朝市』は、まるで宝探しの冒険。そこには丹波布や陶器など、古都らしい魅力あふれる品々が満載です。朝市の個性とその余韻を辿りましょう。
▼他の要約小説も読む▼
>>【要約小説】名作のあらすじを読もう!小説特集京都に魅了された柳宗悦と朝市への情熱
柳宗悦が京都に住んだのは大正末から昭和8年までの約9年間。その中で彼の心を引きつけたのが「朝市」でした。朝市とは、月のうち特定の日時と場所で開催される市で、最も著名なのが東寺の「弘法の市」と北野天満宮の「天神の市」。ここでは、古着や陶器、民芸品など多岐にわたる品が並び、京都ならではの手工芸文化を垣間見ることができます。
下手物の美学―「民芸」の誕生
朝市で柳が気付いたのは、地域の人々が「下手物」と呼ぶ日用品の美しさでした。下手物とは、雑器や民器のような日常使いの素朴で実用的な物を指します。この美しさを認識し評価した彼は、「民芸」という新しい言葉でこれを表現し、後にこの言葉が広く浸透するきっかけとなりました。その背景には、昔ながらの技術や素材を用いた温かみのある商品たちが存在したのです。
掘り出し物との出会い―丹波布と陶器の逸品
柳が特に魅了されたのが丹波布。手紡ぎの糸や草木染めならではの自然な色合い、美しい縞模様の布は、掛布団や仕服など多用途で使用されました。また、彼は陶器の「大捏鉢」も発見。昭和四年、わずか二円で購入したこの大皿の価値に驚き、その後も民窯の歴史を追い続けました。これらは、彼の審美眼と探究心によって掘り起こされた文化の遺産です。
今でも息づく京都の朝市
「京都の朝市」は、柳宗悦が心から愛し、文化的な探究を深めた場所。現代でも、このような市場は自由で探索心をかきたてます。名の知れた名品でなくとも、その場ならではの個性や美しさに満ちた品々が彼を、そして私たちを魅了しました。正確な知識ではなく直感が頼りにされるこれらの市は、まさに未踏の猟場と言えるでしょう。
まとめ
柳宗悦の『京都の朝市』は、地域文化と日常の美が交錯する独特な空間を描き出しています。簡素で素朴な「民藝」の世界が成立するプロセスや、掘り出し物への彼の情熱が生き生きと語られます。丹波布や陶器などの出会いを通じて、私たちは日本の伝統工芸の深みと魅力に触れることができるでしょう。この小説を通じ、京都の朝市を訪れたくなるのは間違いありません。ぜひ古都の空気感を想像しながら本書を手に取ってみてください。
▼あわせて読みたい▼
>>江戸川乱歩の『宇宙怪人』あらすじ紹介。円盤から飛び出してきたのは、異様な怪人!現実を超えた怪奇なストーリー >>【戦後80年に読みたい小説】夢野久作の『戦場』あらすじ紹介。想像を絶する「戦場のリアル」そして人間倫理の葛藤 >>柳田國男の『狐の嫁取といふこと』あらすじ紹介。女性の人生に転機に関わる「狐の秘密」
※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。
▼関連書籍を読む▼
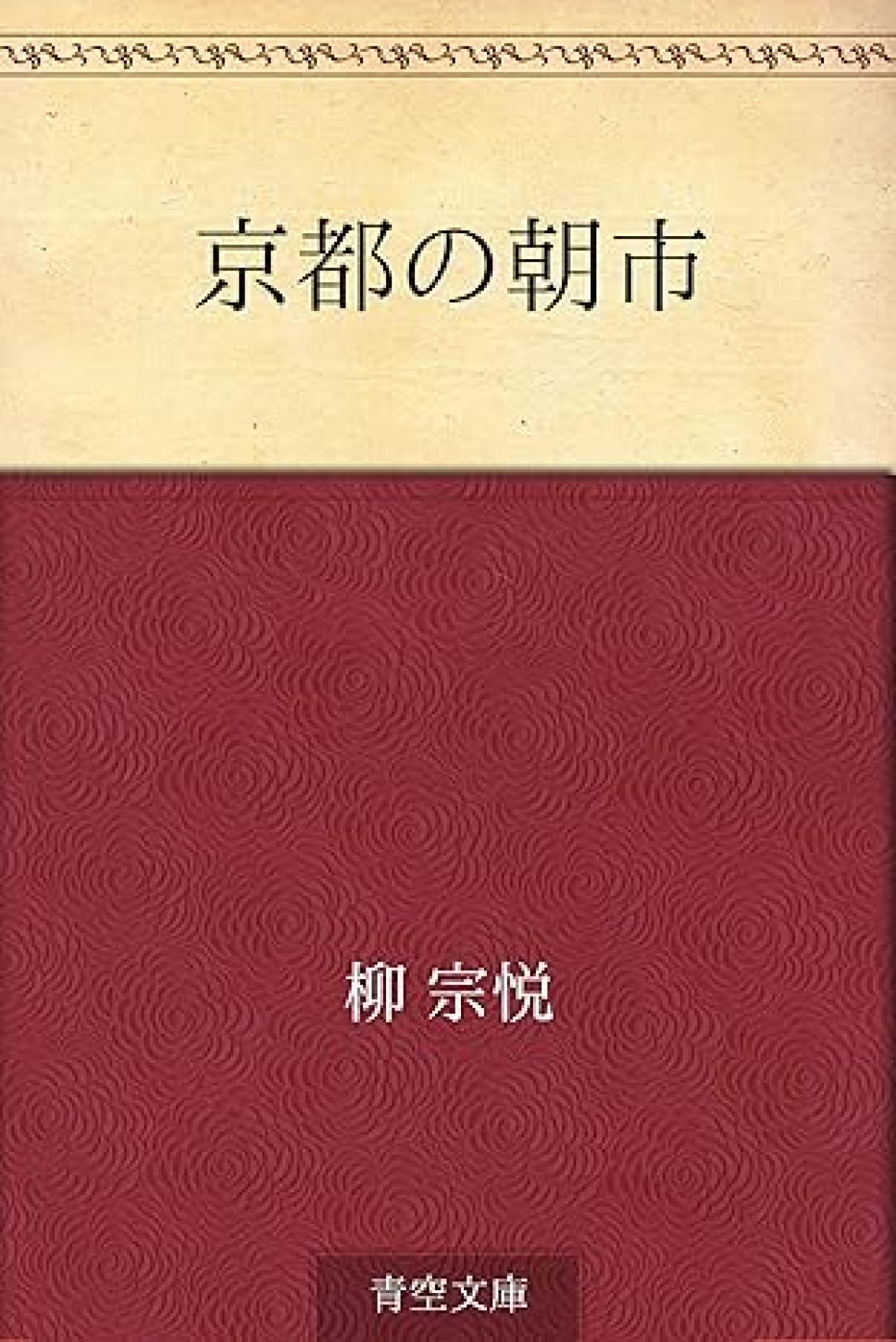
京都の朝市
柳宗悦(著)
青空文庫(刊)
※詳細は以下のボタンへ






















