【要約小説】名作のあらすじを読もう!
三木清の『如何に読書すべきか』あらすじ紹介。心を豊かにする読書習慣の創造とは?
公開日
更新日
ゆうゆうtime編集部
『如何(いか)に読書すべきか』は、読書を通じて心を豊かにし、生涯学び続ける方法を探求する哲学的エッセイです。読書の習慣化、古典の重要性、さらには個々に合った読書法の発見を通じて、真の教養を育むための道筋を示しています。このエッセイを通じて、読書の奥深さや楽しさを再認識することでしょう。
▼他の要約小説も読む▼
>>【要約小説】名作のあらすじを読もう!小説特集読書を習慣に—時間を作り出し人生を彩る
本作の冒頭では、良い読書習慣を一生の財産として確立する重要性を説いています。筆者は「読書するための時間がない」という言い訳を鋭く退け、忙しい日々の隙間時間を有効活用することで読書の習慣を育む術を語ります。朝や夜にわずかな時間でも設けることで、知識や教養が積み重なり、人生が豊かになると述べています。また、読書には心を落ち着かせる力があり、忙しい現代社会においてその価値がさらに際立つと論じられています。
読書は技術—個性に合った読書スタイルを発見する
本書内で特にユニークなのは、読書を「技術」として捉え、個々の気質に沿った読書法を見つける重要性を強調している点です。読書初心者に多い「濫読(みだりに多くの本を読むこと)」についても研究的・冒険的な読み方として一定の意義を認めつつ、最終的には精読へとステップアップする必要があると述べています。「自分に適した本やその著者との出会い」こそ、知識を得る上での最大の喜びとなるのです。
古典を読む—過去と現在を結びつける力
筆者は、特に「古典」を読むことの重要性を力説しています。古典は時代を超えて評価されてきた書物であり、読者の鑑識眼を養う最高の教科書とされています。古典を「安心して何度でも読む価値のある作品」としつつ、新しい問題意識を持つために時には新刊書にも目を向ける大切さも説いています。この二つをバランスよく読むことで、古典の持つ深遠な価値がさらに引き立てられると述べています。
正しい読書と繰り返し読む喜び
「正しく読む」ためには、自分のための本を選び、ゆっくりと繰り返し読むことが鍵とされています。表面的な読み方や、単に読者向けの解説書だけに頼ることを戒め、原典そのものを読むべきと述べます。繰り返し読むことで、初読時には気付けなかった新たな発見や深い理解が得られます。読者が著者と対話し、自らの考えを深めることこそが、読書の最大の醍醐味だと筆者は強調します。
読書と人生の冒険—批評から発見へ
最後に筆者は「発見的読書」のすすめを述べます。本をただ読むだけでなく、そこから問題提起を受け、自らの思索を進めていくべきだ、という考えです。著者の意図を尊重しつつも、読者自身の視点や経験を取り入れることで深い学びを得ることができると言います。読書が単なる知識の吸収ではなく、人生そのものへの挑戦を意味すると暗示しています。
まとめ
『如何に読書すべきか』は、ただの読書指南書ではありません。読書を通じて人生をいかに豊かにし、心の奥底で「発見」をもたらすかを探求した哲学的エッセイです。本書は読書初心者から愛好家まで、多くの人に読書の奥深い楽しみを教えてくれます。そして大事なのは、「何を読むか」と「いかに読むか」に留まらず、「自分を見出す読書」というテーマを追求している点です。自分だけの読書スタイルを発見し、知的な冒険を広げることで、読書そのものが人生を彩る大きな力となるのです。ぜひ、このエッセイを手に取って、読書の新たな可能性を見つけてみてください。
▼あわせて読みたい▼
>>室生犀星の『愛の詩集』あらすじ紹介。―孤独と愛、詩に込められた温かさと苦悩とは? >>山村暮鳥の『小川芋銭』あらすじ紹介。日本画家・小川芋銭の芸術性と人生観に触れる旅 >>下村湖人の『青年の思索のために』あらすじ紹介。時代を超えて読みたい、人生の教訓とは?
※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。
▼関連書籍を読む▼
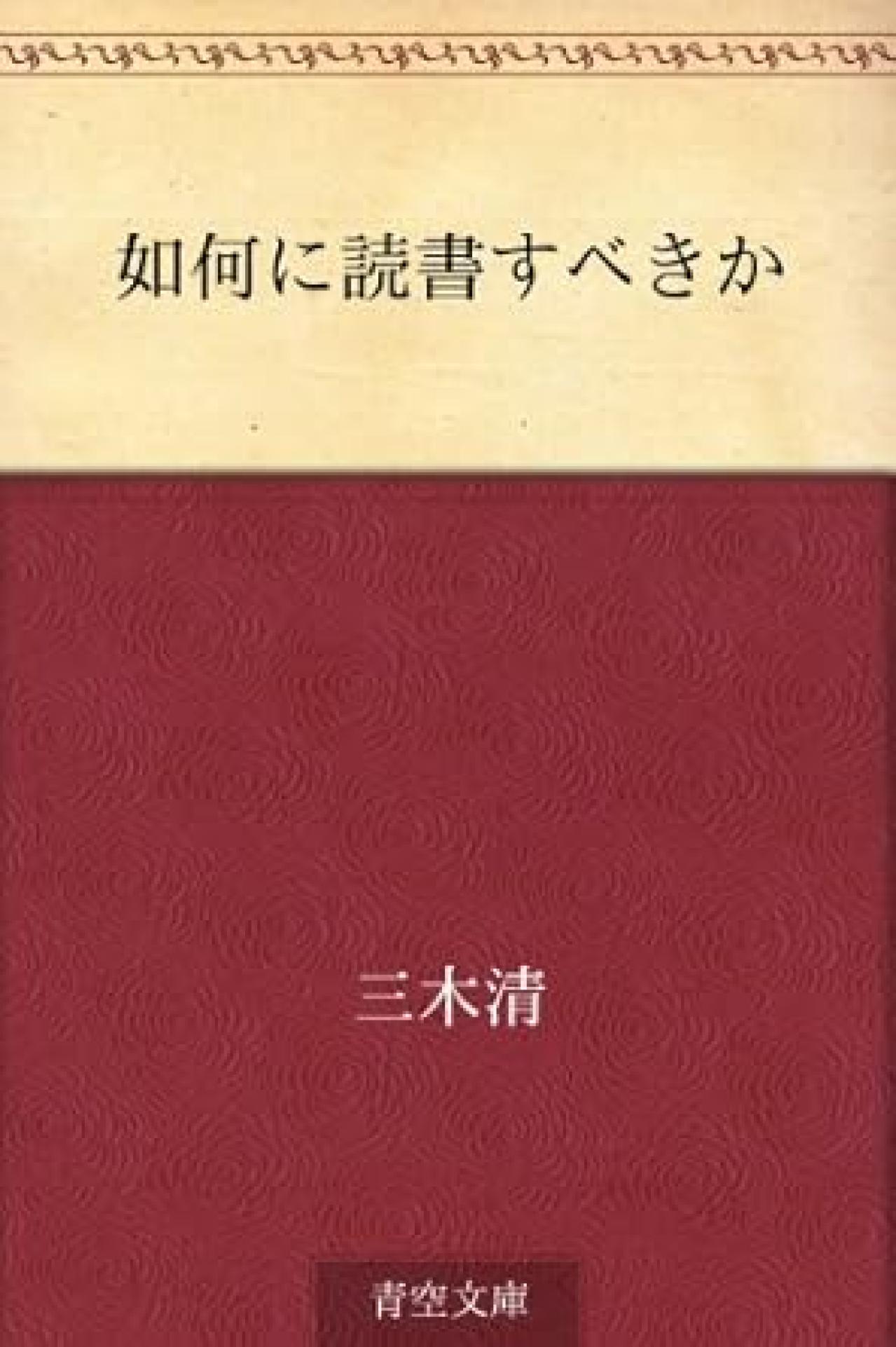
如何に読書すべきか
三木清(著)
青空文庫(刊)
※詳細は以下のボタンへ






















