【要約小説】名作のあらすじを読もう!
【戦後80年に読みたい小説】岸田国士の『従軍五十日』あらすじ紹介。戦場の現実と人間の心を見つめる旅
公開日
更新日
ゆうゆうtime編集部
戦後80年である2025年に特に読みたい小説を紹介します。戦時中の中国大陸を舞台に『従軍五十日』で描かれる、戦場のリアルと人々の姿。岸田国士が体験と筆で綴った、戦争とは、人間とは、を考えさせる文学的記録です。
▼他の要約小説も読む▼
>>【要約小説】名作のあらすじを読もう!小説特集戦場の記録、それは「従軍の五十日」
1940年に発表された『従軍五十日』は、岸田国士が「従軍作家」として中支戦線に赴き、約50日間の視察と体験を元に書かれた作品です。戦争の現実に触れる旅路は、時折悲劇的であり、時折温情深いもの。彼の目で見た戦場の人間模様が綴られています。上海から南京、その後の揚子江への旅路と地域巡察を通じ、占領地の住民、兵士、日本軍の政策の実態などが描写されました。
目撃した戦争のダイナミズム
岸田は戦況の最前線で、危険と隣り合わせの軍隊の動きや、敵味方の攻防を目撃します。昼夜問わず戦う兵士たちの姿を目の当たりにし、その勇敢さや忍耐力に感銘を受けました。一方で、一般人である彼自身が体感した恐怖や、戦場における人間の生存本能についても探ります。それと同時に、兵士たちが示す人間らしさ、例えば戦闘後の緊張感に満ちた一服の安らぎも描かれました。
戦争と住民―宣撫や反発の現場
戦地にある日本軍が試みたのは単なる軍事行動ではなく、占領地住民への「宣撫(せんぶ)」です。住民との関係性をいかに築くべきか、その試みと失敗、新たな挑戦が語られます。例えば、日本語教育や臨時学校の設立、架け橋となる通訳の存在、慈善病院の運営などが描かれました。しかし一方では、冷淡な住民の反応もあり、その背景には根深い反感や恐怖が存在します。岸田はこれらの多面的な現象を冷静に記録しました。
最前線の思索と未来の問いかけ
岸田は、戦争がいかに多様な側面を持つかを描くとともに、日本の軍や文明が支那民衆にどのように受け止められるか、その後の未来についても考察します。彼の文章には、戦地での経験を通じて得た現実認識、そして日本という国の未来への希望と疑問が随所に込められています。それは単なる目撃者の記録を超え、当時の社会風潮に一石を投じるような文学的挑戦ともいえるでしょう。
まとめ
『従軍五十日』は、岸田国士が体験を通じて描き出した戦場と人間模様を記録した記念碑的な作品です。鮮烈な光景描写はもちろん、戦争という特殊な状況下での人と人との関係性、国家と民衆のはざまにある葛藤を描いたこの記録は、当時の日本人に何を伝えたかったのか、その答えを深く考えさせられる内容となっています。一方で今日の読者にとっても、この作品は過去の戦争を振り返り、平和の持つ本当の意味を考えさせる機会を与えてくれるでしょう。
▼あわせて読みたい▼
※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。
▼関連書籍を読む▼
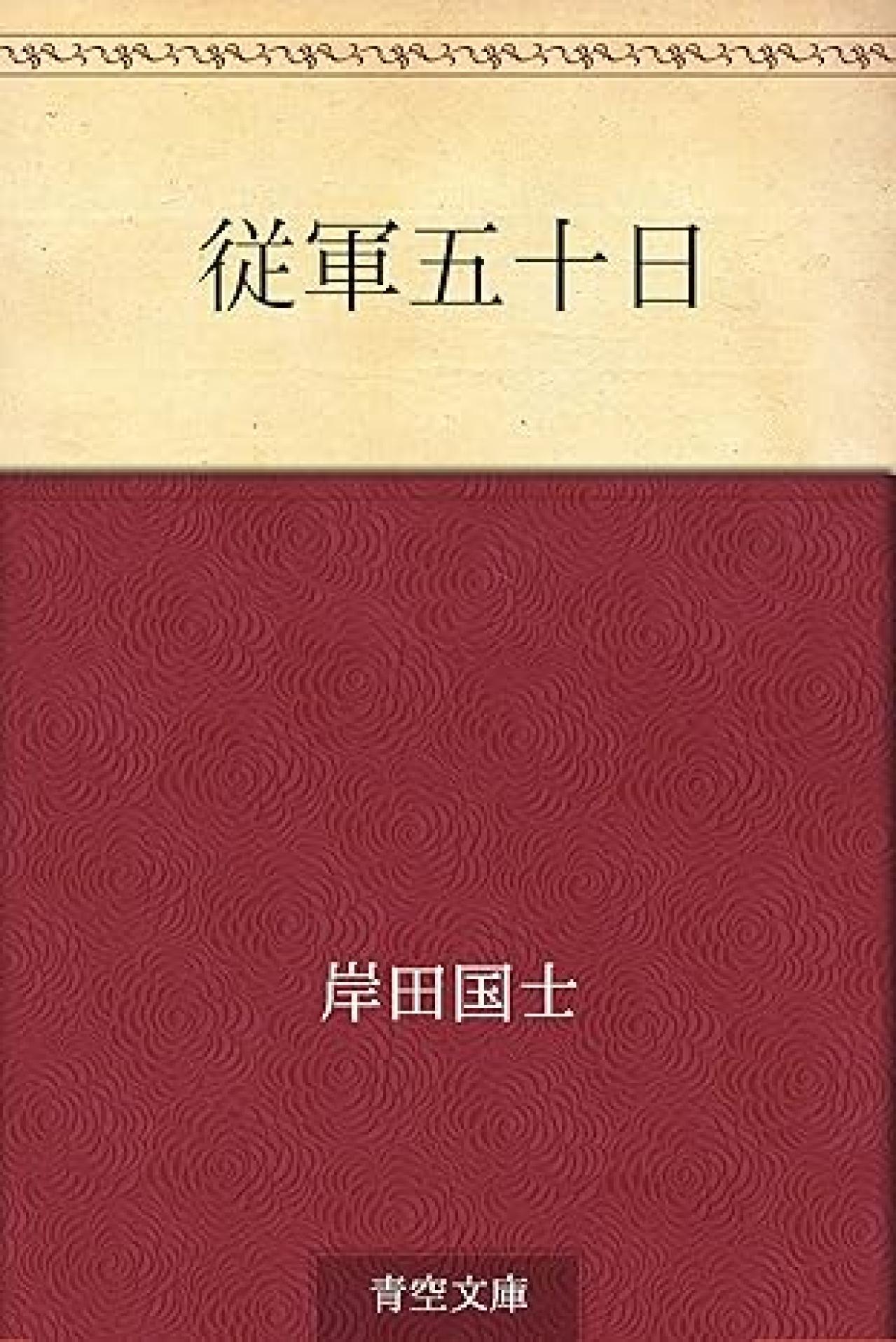
従軍五十日
岸田国士(著)
青空文庫(刊)
※詳細は以下のボタンへ






















