【要約小説】名作のあらすじを読もう!
【戦後80年に読みたい小説】桐生悠々の『関東防空大演習を嗤う』あらすじ紹介。防空演習に対する冷徹な批評と風刺
公開日
更新日
ゆうゆうtime編集部
戦後80年である2025年に特に読みたい小説を紹介します。『関東防空大演習を嗤(わら)う』は、日本の防空演習を風刺しつつ、戦争の現実や航空技術の進歩を浮き彫りにする批評的な小説です。その核心とは?
▼他の要約小説も読む▼
>>【要約小説】名作のあらすじを読もう!小説特集関東防空大演習の壮大さとその限界
物語の幕開けは、関東地方で実施された大規模な防空演習の描写から始まります。この演習には多数の航空機が参加し、全国中継されるほどの注目を浴びました。しかし著者は、その壮観ぶりに感心するだけでなく、もしもこれが実際の戦闘だったならば、どれほどの惨状が引き起こされていたかと指摘します。著者は、市民が恐怖や損害への不安を抱きつつも、実際にはこのような演習は役立たないのではないかと批判的な目を向けます。
防空作戦の論理的矛盾
著者は、防空演習の中で帝都の上空に敵機を迎え撃つこと自体が、すでに敗北であると指摘します。敵機が実際に帝都に到達する前に、もっと効率的かつ決定的な対策を講じるべきだと主張。日本海や太平洋の沿岸で敵機を迎撃し、帝都の空に侵入させない防空戦略が必要だと述べています。この議論を通して、作戦計画の不十分さが浮き彫りになります。
技術革新と防御不能の空爆
物語の後半では、航空技術の進歩が描かれ、その現実が防空演習をさらに無意味なものにする様子が示されます。著者は、飛行機の速度や風向を計算する科学技術の正確さを挙げ、ロボット操縦でも爆撃地点に命中できる状況を描写。この進化によって、防空体制がいかに脆弱(ぜいじゃく)で滑稽に映るかを強調します。また、赤外線技術によって敵の位置が丸見えになる時代が到来することも指摘し、従来型の防空戦略の無力さを明らかにしています。
消灯計画と演習の滑稽さ
大規模な防空演習の一環として暗闇を作り出す消灯計画。しかし著者は、これも市民に無駄な不安を与え、混乱を招くだけだと主張します。その上、「観察の目を焼き付ける現代科学」の前では、暗闇も無意味であると皮肉っています。さらに、過去の戦例からも防空する側の難しさを示し、空撃される側が圧倒的に不利である現実を強調します。
まとめ
『関東防空大演習を嗤う』は、防空演習に対する冷徹な批評と風刺的な視点によって、戦争の残酷さや無力感、そして科学技術の進歩がもたらす新たな疑問を読者に投げかけます。壮観なはずの演習は、作戦の妥当性や戦術の限界を浮き彫りにし、防衛そのものの在り方を問う内容となっています。本作は、読者に戦争の滑稽さとリアルな恐怖を再考させる力を持つ、文学としても批評としても優れた一作です。読後に残るのは、防空という言葉の奥深い意味への問いです。
▼あわせて読みたい▼
※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。
▼関連書籍を読む▼
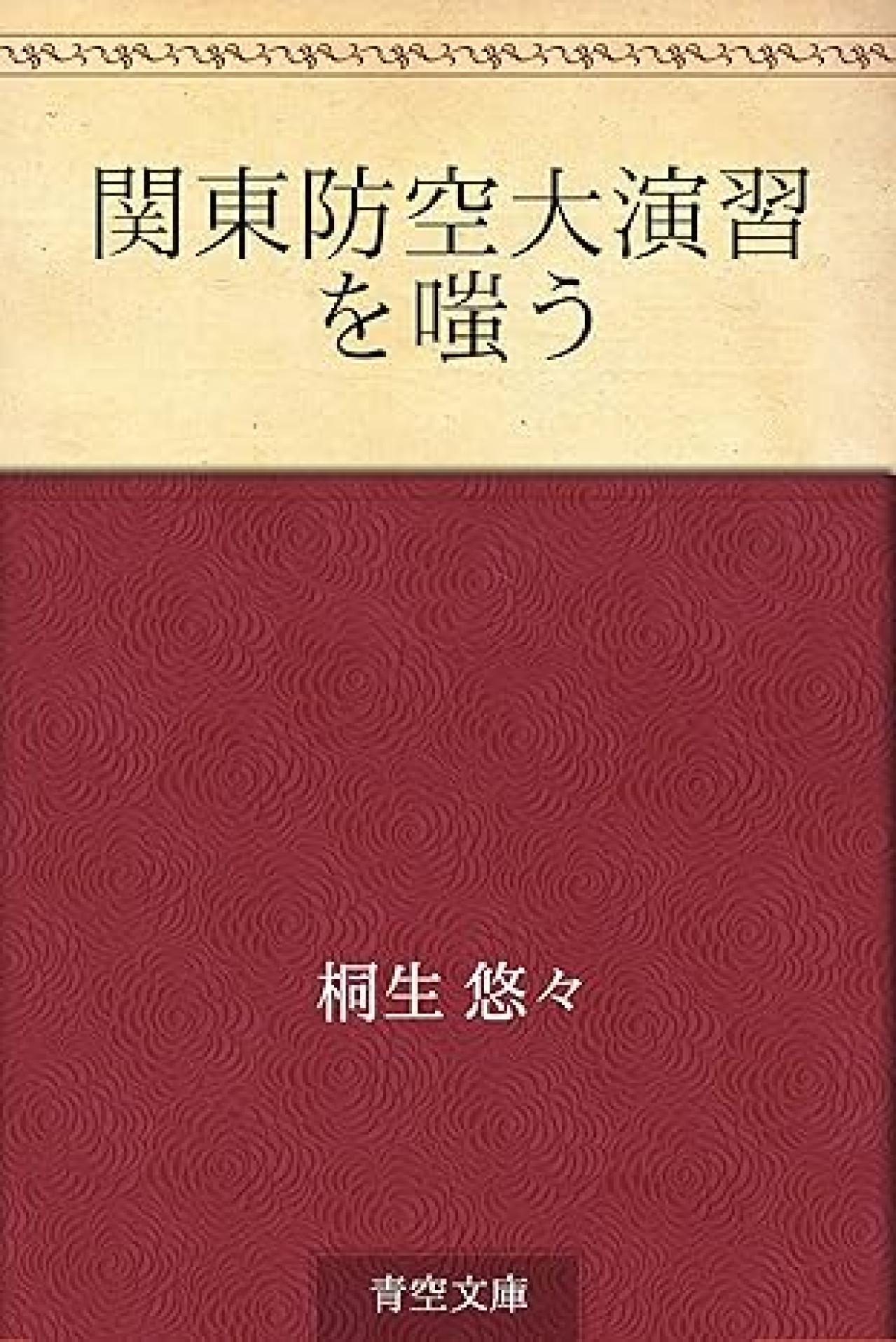
関東防空大演習を嗤う
桐生悠々(著)
青空文庫(刊)
※詳細は以下のボタンへ






















