【要約小説】名作のあらすじを読もう!
柳宗悦の『現在の日本民窯』あらすじ紹介。琉球壺屋から北国の窯まで、柳宗悦が描く日本の民窯の美とその支え手たち
公開日
更新日
ゆうゆうtime編集部
柳宗悦の『現在の日本民窯』は、九州から東北まで、各地の民窯が抱える魅力と課題を描いた珠玉の文学的ドキュメンタリー。歴史、技術、そして人々の暮らしを通じて、窯場の奥深き世界を紹介します。
▼他の要約小説も読む▼
>>【要約小説】名作のあらすじを読もう!小説特集日本全国を巡る民窯の記録
本作は柳宗悦とその仲間が日本全国を旅し、その地に息づく民窯の現状を記録したものです。「民窯」とは、伝統的手法を用いた日用陶器を作り続ける窯のこと。作者らは九州の南端から四国、中国、北国まで40数カ所を訪ね歩き、その窯の歴史や産物を記しました。現地の人々の生活や、窯を取り巻く環境なども描かれ、まさに生きた民藝(みんげい)の記録と言えるでしょう。
壺屋:琉球の伝統が息づく窯
物語の最初に訪れる琉球壺屋。ここはかつて那覇郊外の村でしたが、市街地拡大に伴い変遷を遂げています。壺屋では「南蛮焼」と呼ばれる素朴な無釉(むゆう)の大つぼから、「上焼」と呼ばれる日常雑器まで、幅広い品が生産されています。特に赤絵を施した鮮やかな陶器や、線彫りを用いたデザインが人々を魅了します。また、品々の背景には南方中国、朝鮮、九州など、他文化との交流が見え隠れし、独特な「咀嚼(そしゃく)」の歴史があります。
北国の特色ある窯場たち
東北地方にも民窯の数々が点在しています。例えば陸前の堤では、雑器における力強い形と釉薬(ゆうやく)の美しさ、羽前成島の地味で堅実な黒釉の技術が特徴です。他にも羽後の楢岡や栗沢といった窯では、粗野ながらも魅力的な形状や色彩の焼物が評価されています。どの窯も地元の伝統や風土に根ざし、少量生産ながらも味わい深い作品を生み出しているのです。
失われつつある窯とその復興への挑戦
一方で、かつて存在した窯の多くが廃絶の運命をたどっています。特に弘前の悪戸窯のように、美しい技術や意匠を持ちながらも途絶えてしまった例も少なくありません。その中で、新たに再出発を試みる陶工や、地元の産業を支えようとする人々の姿が描かれ、彼らの挑戦が読者の心を打ちます。
土地のものを愛する心が未来を作る
本土や輸入品が重視される現代、地元の焼物を見過ごす人々への戒めも本作には含まれています。壺屋の良質な伝統的工芸品が下賤(げせん)な品とされ、土地で敬遠されることへの嘆き、土地の価値を再発掘する必要性が述べられます。「地方色を持つ窯が未来にも尊敬されねばならない」、そんな強い言葉が浮かび上がります。
まとめ
『現在の日本民窯』は、日本全国を巡り、窯場およびそこに根付く伝統工芸の姿を丹念に描いた文学的ドキュメンタリーです。柳宗悦はその中で、各窯が持つ歴史的・文化的背景を掘り下げながらも、現代の課題に鋭く切り込んでいます。特に琉球壺屋の多様性や、北国に息づく力強い窯の仕事は、読者に好奇心と感慨を抱かせることでしょう。一方、近代化の波に埋もれつつある窯への惜しみない賛辞と、その復興を願う声が、未来への希望となります。この本は窯や器に宿る「人と土地の物語」を知りたい方にとって必読の一冊です。ぜひこの機会に、窯場の世界を一歩深く訪れてみてください。
▼あわせて読みたい▼
※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。
▼「柳宗悦」の関連書籍を読む▼
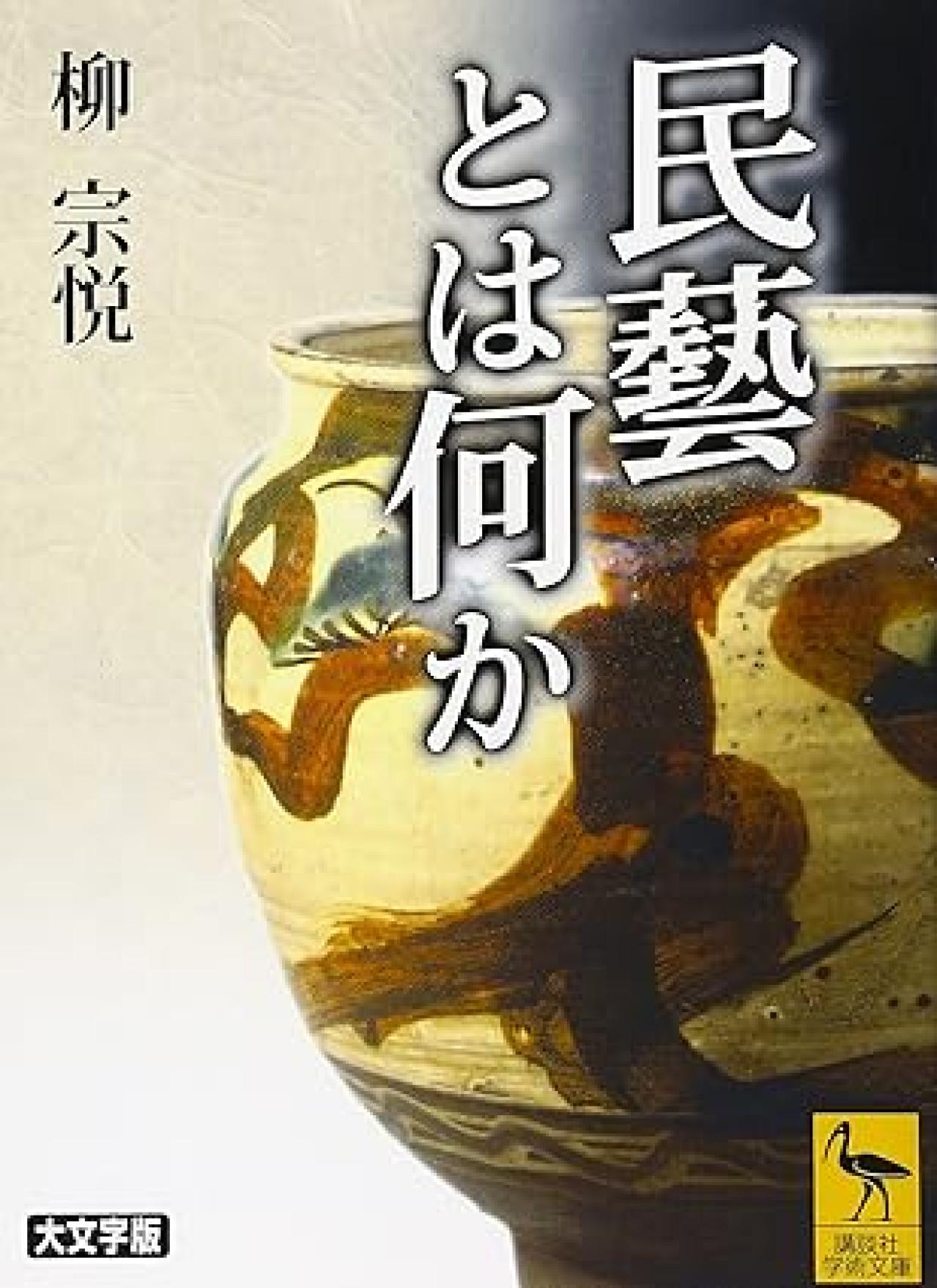
民藝とは何か
柳宗悦(著)
講談社学術文庫(刊)
※詳細は以下のボタンへ






















