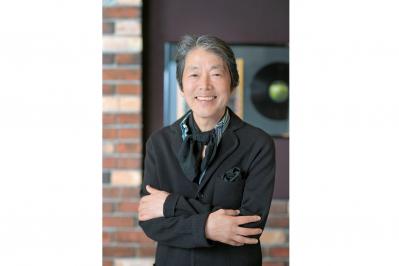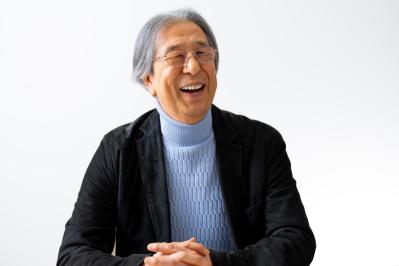【要約小説】名作のあらすじを読もう!
高村光太郎の『黄山谷について』あらすじ紹介。稚拙で荘厳!?唯一無二の書家が魅せる美とは
公開日
更新日
ゆうゆうtime編集部
黄山谷(こうざんこく)の書を思わず毎朝見つめてしまう。平凡なようで奇妙、稚拙なようで荘厳(そうごん)。『黄山谷について』はその不思議な魅力を、作家ならではの鋭い感性で描きます。感動のすべてをあなたへ。
黄山谷の書、その唯一無二の個性
タイトルに登場する黄山谷とは中国宋代の三大家の一人として名をはせた書家。彼の書は、一見「まずい」と評されることさえある独特なものです。他の蘇東坡や米元章の書が鮮やかな技巧を誇る中、黄山谷の書は稚拙さと不器用さに満ちていますが、そこには不思議な魅力が潜んでいます。そしてその魅力は技巧を超えた圧倒的な存在感を宿しているのです。
作家の視線で見る「伏波神祠詩巻」
物語の筆者は、アトリエの壁に掲げられた黄山谷の『伏波神祠詩巻』の冒頭部分の写真に心を奪われます。毎朝起きるたびに自然とその書に目が行き、まるで新しい世界を見るような驚きを受けるという不思議な感覚。この詩巻に向き合うことで1日の始まりにエネルギーをもらえるようです。書の奇妙な具合が心をつかむその理由を、筆者の描写から感じ取ることができます。
「まずさ」の中にある荘厳、「稚拙」の中に宿る品位
黄山谷の書は一字一字をよく見るとまるで初心者のように見えます。線がたるんだり、文字の大小や方向さえ気にしなかったり。しかし、その不規則さの中には圧倒的な気迫と精妙さが宿り、見る者に深い感動を与えます。その自由さはむしろ美しさを超越し、力強さと品位を持っています。他の書家にはない非凡さで、黄山谷の書はあらゆる美の基準を二分してしまうものなのです。
背中の病から生まれた奇跡の詩巻
黄山谷がこの『詩巻』を書いたとき、背中に大きなできものができていて手も思うように動かなかったというエピソードがあります。それでも書き上げられた詩巻は、むしろその不自由さがなければ生まれなかったのではないかと言える作品。筆の「ぎゅっ」とした強さ、自由でありながら乱暴でない手触り。そのすべてが、この書を筆者の心に刻み込む要因となっています。
まとめ
『黄山谷について』は、宋代の書家・黄山谷の書道の不思議さと、筆者自身の感銘を余すところなく描いた文学作品です。その特徴的な不器用さや自由さの中に、人間の持つ底知れぬ力や美の本質が見えてきます。見るたび、新鮮に心に響く黄山谷の書は、毎日を新しく生きるエネルギーすら与えてくれます。この小説は芸術とは何か、そしてその背後にある人間の意志と美を考えさせてくれる一冊です。芸術に興味がある人や、美に新しい視点を持ちたい方には心に刺さる内容になっています。黄山谷の書が持つ魅力に触れてみれば、あなたもそのとりこになることでしょう。
▼あわせて読みたい▼
※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。
▼関連書籍を読む▼
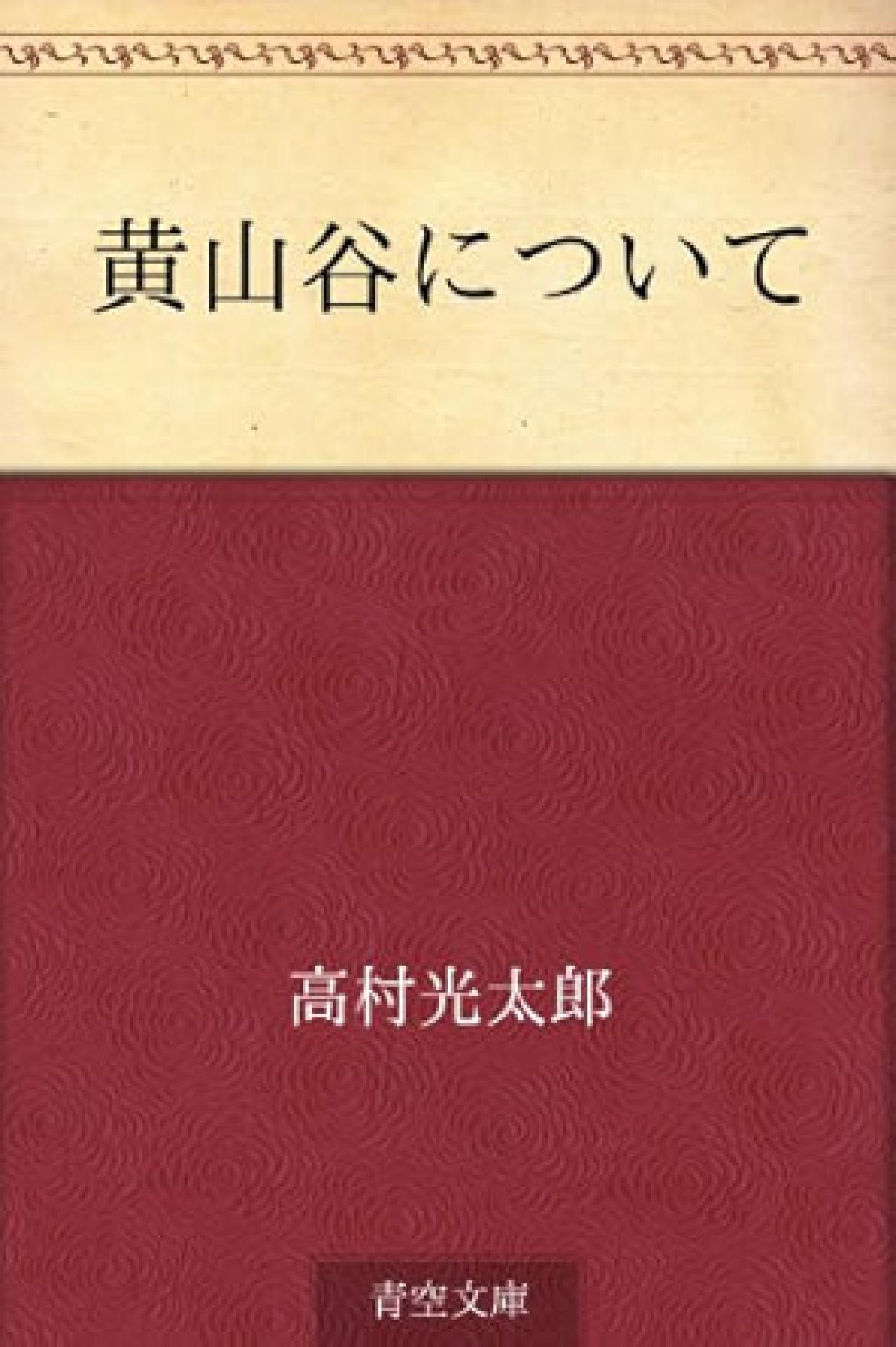
黄山谷について
高村光太郎(著)
青空文庫(刊)
※詳細は以下のボタンへ












![【ザ・タイガース】旋風のその先に。別れの裏にあった、知られざる物語[79歳・瞳みのるさんのターニングポイント#2]](/images/articles/thumb20260115vs9fse202645835985.jpg)