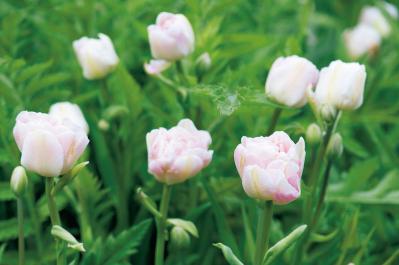【ガーデニング】7月のバラ育てですべきこと。ゴマダラカミキリに要注意!
公開日
更新日
吉原美奈子
7月は天気の変動が大きく、バラにとって過酷な環境が続くこともあります。特に、二番花が咲いたあとはバラをこまめに見る機会が減り、そのすきを狙うように害虫に食害されたり、産卵されることも多いので注意が必要です。
▼前回はこちら▼
>>【ガーデニング】6月のバラのお手入れ。花がら切りと肥料、枝の正しい切り方とは?バラの天敵、ゴマダラカミキリ
黒い体に白い斑点を持ち、長い触角が特徴的なゴマダラカミキリ。
昆虫マニアにはかっこいいと思われるかもしれませんが、バラ愛好家にとっては一目見ただけでぞっとする害虫です。
7~8月にこのゴマダラカミキリの姿を見たら、とにかく捕殺することが大事です。
この時期、ゴマダラカミキリは枝の表皮をかじるなどの被害を与えますが、実はこの被害自体はそれほど深刻なものではありません。
本当に怖いのは、成虫がバラの株元に産卵することで、卵は数週間でテッポウムシと呼ばれる幼虫になります。
このテッポウムシがバラの茎に入り込んで内部を食害するのですが、その様子はもちろん外からは見えず、茎の内部が食い尽くされるとバラは枯れてしまいます。
バラが突然枯れてしまったという話を耳にすることがありますが、その原因がテッポウムシの被害であることは多いのです。
ですから、親のゴマダラカミキリが産卵しないよう、庭を見回って見つけたらすぐに捕殺することが大事です。
二番花が咲き終わると庭仕事も一休みとなり、バラを見回る回数も少なくなりがちですが、油断しないように注意しましょう。
飛来を防ぐため、7~8月に2、3回、園芸用キンチョールを株に噴霧するのも一法です。
ゴマダラカミキリの幼虫の見つけ方
ゴマダラカミキリは7~8月ごろに株元の土に産卵します。
孵化して幼虫のテッポウムシとなると、バラを食害しながら糞を出します。
株元に穴が開いていて、そこにおがくず状の糞が盛り上がるように出ていたらテッポウムシが潜んでいる証拠なのですぐに駆除が必要です。
前述した園芸用キンチョールに添付のノズルをつけ、穴に差し込んで5秒ほどスプレーし、終わったら穴を土でふさぎます。
穴は木工用ボンドでふさいでもよいでしょう。
テッポウムシは幼虫のまま土中で越冬し、成長した翌年もバラの茎の内部に入り込んで被害を与え続けます。一度、穴を見つけたら継続して防除に努めてください。
テッポウムシの被害に悩まされている人は多く、SNSなどではいろいろな薬剤の使用が報告されています。
トラサイドA乳剤もその一つで、バラへの適用はありませんが、有効だとする声も多いようです。