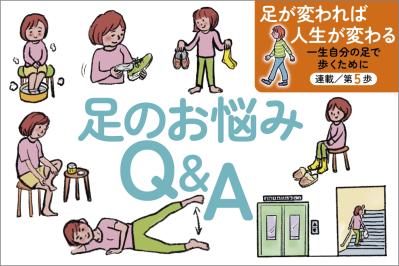「ブクブクうがい」と「ガラガラうがい」はどちらが正解?【花粉症対策】鼻やのどの粘膜を鍛える簡単な方法
鼻うがいの上手なやり方
「鼻うがい」は、鼻の中に水を入れて洗い流す方法です。
鼻の中の異物を取り除き、粘膜を加湿できるので、鼻の粘膜の状態を改善させることができます。
効果の高い鼻うがいですが、鼻うがいをするのに抵抗がある人は少なくありません。プールなどで鼻に水が入って痛くなった経験があるからだと思います。鼻の粘膜には、痛みを感じ取る「三叉神経」があり、それが刺激されるとつーんとした痛みを引き起こすのです。
これは、ワサビを食べて鼻がつーんとするのと原理は同じです。のどから鼻腔にワサビ の刺激物質が入り、三叉神経を刺激したのです。ワサビを食べたときの感じはにおいでも味でもなく、痛み刺激なのです。
鼻うがいをするときは、三叉神経を刺激しないように水温と浸透圧を調整しましょう。約38~40℃のお湯を使い、生理食塩水と同じ0.9%になるように食塩を入れることがポイントです。そうすれば鼻が痛くなることはありません。また、鼻うがい用の器具や薬剤が販売されているので、それを使うのもおすすめです。
鼻に水を入れると、水がのどに流れ込んでむせることがあります。そうならないように、鼻うがいをするときは、「エー」と声を出します。
鼻に入った洗浄液は、①洗浄液を入れた鼻孔、②反対側の鼻孔、③鼻の奥を通って口から、のいずれかから出ます。どこから出るかは、こだわらなくてもかまいません。
水は軽く鼻に入れるだけで大丈夫です。水を強く入れすぎたりすると耳に水が流れ込み、中耳炎を起こす可能性があるので注意してください。
鼻うがいは、1日1~2回を目安に、3回までにしましょう。
歯をみがいてリスクを減らす
歯を失うと、しっかり飲み込めなくなったり、言葉をうまく話せなくなったりするので、 口の中をきれいにすることが大切です。歯をみがくことも含め、口の中をきれいにすると、病原体への感染リスクを下げ、口臭を減らすこともできます。
歯みがきは1日3回、寝る前には入念にみがきましょう。
ふつうの歯ブラシでしっかりと歯をみがくのは、手間がかかります。電動歯ブラシを使うのもよい方法です。電動歯ブラシはこまかく振動するので、早くてきれいに歯をみがくことができます。
歯だけでなく、歯ぐきの健康を守ることも大事です。
歯ぐきが炎症を起こすと、歯ぐきが小さくなって歯を維持できなくなります。歯を失わないためには、歯と歯ぐきの間をきれいにして歯周病を防ぐことが大切です。
ただし、歯ブラシを歯ぐきに強く押しつけると歯ぐきを傷めてしまうので、歯と歯の間の歯垢は歯間ブラシやフロスを使って取り除きます。
フッ素は、歯の再石灰化に効果があります。みがいたあと、あまり口をすすぐとフッ素も洗い流されてしまいます。歯みがきをしたあとは、2〜3回のすすぎにとどめましょう。
歯みがき粉には口の中を爽快にする成分が含まれており、みがき足りなくてもみがいた気になってしまいがちです。たまには歯みがき粉を使わず、みがき残しがないかを確認しながらみがいてみましょう。
甘いものや炭酸水などに含まれる酸は、歯のエナメル質を傷つけるので、摂取はほどほどに。気がつかないうちに虫歯ができたり、歯周ポケットが汚れたりすることがあります。半年に1回は歯科医院でチェックしてもらい、歯のクレンジングをしてもらいましょう。