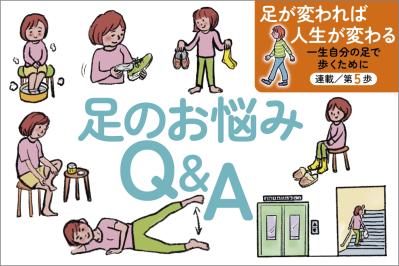「ブクブクうがい」と「ガラガラうがい」はどちらが正解?【花粉症対策】鼻やのどの粘膜を鍛える簡単な方法
鼻やのどの粘膜を自分で傷つけない
鼻やのどの粘膜がしっかりと働くためには、粘膜がきれいな状態でなければなりません。鼻(のあな)をさわったり、強くせき払いをしたりといった粘膜を傷つける行為はできるだけ避けましょう。粘膜を傷つけた場合でも、それを治す方法を知っておくと役立ちます。
鼻やのどの粘膜を傷つけないための、具体的な方法を紹介していきましょう。
鼻にやさしい、はなのかみ方
自分の指で鼻(のあな)をさわるのが癖になっている人は多くいますが、鼻はできるだけさわらないようにしましょう。
鼻をさわると鼻の粘膜が荒れてかさぶたがつきやすくなったり、鼻血が出やすくなったりしてしまいます。すると、さらに鼻の違和感が増し、よけいに鼻をさわることになります。
私も作業に集中すると、気づかないうちに鼻を指でさわってしまいます。鼻の奥が痛くなり、そこからのどに炎症が広がるということを繰り返していました。
鼻をさわらないようにしたいときは、マスクをつけるようにしています。そうすれば指が直接鼻に触れることはなくなり、鼻の粘膜に傷がつきません。
粘膜に傷をつけないようにするためには、はなのかみ方も大切です。鼻にやさしいかみ方を知っておきましょう。
やわらかいティッシュペーパーを使い、ゆっくり片方ずつかむようにします。はなを両方とも一度にかむと耳の中に鼻汁が流れ込んでしまい、耳がつまったようになったり、中耳炎の原因になったりします。
鼻毛は引き抜かずに、外から見えない程度に毛先だけを切りそろえるようにしましょう。無理やり引き抜くと炎症が起こり、鼻がつまることがあります。
鼻毛は、鼻から入る空気から大きなごみを取り除く役割を果たしています。鼻毛がなく なると大きなごみがそのまま鼻の中に入り、粘膜が傷つきやすくなります。
鼻毛の処理などで鼻の入り口が傷ついてしまった場合は、早めのケアが必要です。鼻の入り口の皮膚や粘膜が傷つくと、かさぶたがつき、鼻がつまりやすくなります。
そのようなときはワセリンを鼻の入り口に塗りましょう。ワセリンは軟膏に含まれる成分で、粘膜を保湿する効果があります。加えて、水をはじく性質もあります。鼻の入り口 は汚れやすい場所なので、傷口に異物が入りやすく、傷がなかなか治りにくいのです。撥水効果がある軟膏を塗ると、傷が汚れるのを防いでくれます。
※この記事は『肺炎・ウイルス感染症にならないのど・鼻の粘膜の整え方』浦長瀬 昌宏著(主婦の友社編)の内容をWEB掲載のために再編集しています。
▼あわせて読みたい▼
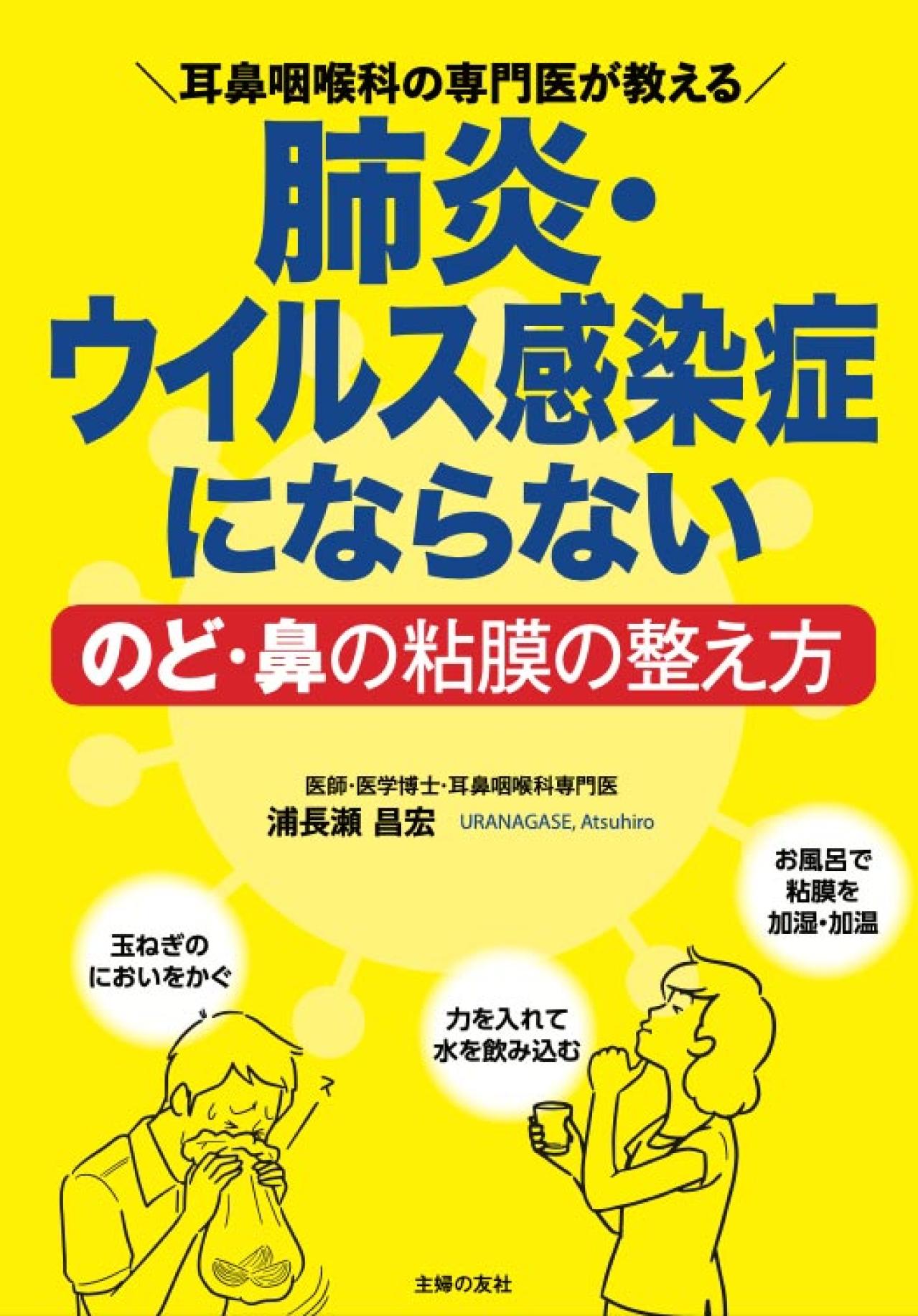
肺炎・ウイルス感染症にならないのど・鼻の粘膜の整え方
浦長瀬 昌宏著
主婦の友社刊
耳鼻咽喉科医はマスクなしでも感染しないのはのど、鼻の粘膜を鍛えているから。だれでもできる粘膜強化で感染症を防ぎましょう。
新型コロナウイルス感染症で日常の光景となり、だれもが手放せなくなったマスク。しかし感染症の最前線で、自らが感染するわけにはいかない耳鼻咽喉科の専門医たちは「重要なのはマスクなしでも感染しないこと」だと声を揃えます。もちろんマスクをすることで感染のリスクが減らせるのは確かです。でもその理由はマスクがウイルスや飛沫を防いでくれるだけでなく、マスクがのど、鼻の粘膜の状態を整えるのに役立つから。決めてはウイルスや細菌の感染の最前線にあるのどと鼻の粘膜のコンディションを整えることだったのです。本書ではだれでもできる粘膜強化法を紹介し、コロナウイルスはもちろんカゼやインフルエンザ、花粉症など多くの感染症対策に役立つ「強い粘膜」「すこやかな粘膜」の作り方を紹介します。
※「詳細はこちら」よりAmazonサイトに移動します(PR)