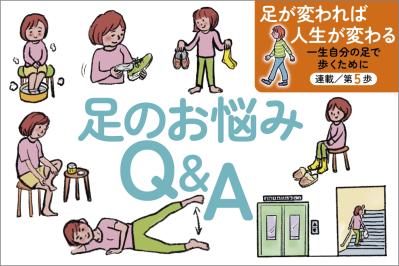姿勢が悪いと、のどの粘膜に悪影響が!?【鼻とのどの粘膜】が整う生活習慣を耳鼻咽喉科医が伝授[花粉症対策]
花粉の飛散状況が気になる季節。のど、鼻の粘膜を鍛えておくと、カゼやインフルエンザ、花粉症などの対策に役立つということを知っていますか? 書籍『肺炎・ウイルス感染症にならないのど・鼻の粘膜の整え方』の著者・耳鼻咽喉科専門医の浦長瀬昌宏先生にアドバイスをいただきます。5回に分けてお届けする最終回は、鼻やのどの粘膜が整う生活習慣について。
▼前回はこちら▼
「加湿器のなかでも特に粘膜にいい種類は…」【花粉症対策】耳鼻咽喉科医がすすめる家電活用法
鼻とのどの粘膜を整えるための生活習慣についてお話しします。
毎日ストレスなく快適に過ごすことは、自律神経をはじめ体調を整えるために最も重要なことです。
もちろん鼻やのどの粘膜にとってもそれは当てはまります。
睡眠中に鼻呼吸をするコツ
1日の3分の1は睡眠時間です。起きているときに粘膜をコンディショニングしても、睡眠中にケアがおろそかになっていると問題が起こります。とくに睡眠中に口呼吸をし続けると、粘膜に悪影響をおよぼします。
【睡眠前の行動】
飲食は睡眠3時間前までにしましょう。睡眠前に食事をとると、胃酸がのどに戻りやすくなり、粘膜を傷めてしまいます。
睡眠前にアルコールを飲まないようにしましょう。アルコールを飲むと寝入りは早くなりますが、睡眠が浅くなって睡眠の質が低下してしまいます。
【環境を整える】
寝室の湿度を50~60%に加湿して寝るようにしましょう。寝室の加湿ができない場合は、寝るときにマスクをつけるのも効果的です。私は寝ているときにはずしてしまうので、マスクをつけて寝ることができません。
落ち着いて寝るために、寝室にはできるだけものを置かないようにしましょう。テレビやスマートフォンを見ながら寝ようとすると、睡眠の質が悪くなります。
【鼻呼吸をする】
睡眠中に口呼吸をしていると、粘膜が乾燥し、舌の根元がのどの奥に落ち込み、呼吸が止まりやすくなります。睡眠中に呼吸が止まるのを繰り返す病気を「睡眠時無呼吸症候群」といいます。日本では3000万人以上がかかっている、いわば国民病です。
睡眠中に鼻呼吸をするためには、次のような方法があります。
・ふだんから鼻呼吸をする
起きているときに口呼吸をしていると、寝ても口呼吸になります。ふだんから鼻呼吸を意識して行うようにしましょう。
・体位を調整する
あお向けで寝ると舌の根元がのどの奥に落ち込みやすくなります。横向きで寝るとイビキが小さくなりやすいです。横向きかうつ伏せで寝ることを心がけましょう。できない場合は、横向きになるための器具もあります。
・肥満を解消する
肥満で舌根部(舌の根元)が大きくなると、気道が狭くなってしまいます。睡眠中は筋肉がゆるんで舌根がのどに落ちやすくなるので、よりいっそう気道が狭くなります。
体重と体脂肪率を適正に保つようにしましょう。
・鼻づまりを治す
鼻がつまって口呼吸になると、舌の根元がのどの奥に落ち込みやすくなります。「アレルギー性鼻炎」「慢性副鼻腔炎」「鼻中隔湾曲症」があれば、早めに耳鼻科で治療を受けることです。とくに鼻中隔湾曲症は手術でしか改善しないので、診断を受けた場合は治療を考えましょう。
鼻翼にテープを貼っても、鼻腔を広げる効果はほぼありません。鼻腔の奥行きはかなり広く、鼻翼の部分だけで鼻がつまっている人はほとんどいないからです。
テープを口に貼っても、寝ているうちにはずれてしまうことが多く、あまり効果がありません。また、鼻がつまっているときは呼吸ができなくなるので、貼ることはできません。

![姿勢が悪いと、のどの粘膜に悪影響が!?【鼻とのどの粘膜】が整う生活習慣を耳鼻咽喉科医が伝授[花粉症対策]](/images/articles/big20250226hrl42r231107335977.jpg)
](/images/articles/big20250226e9qw5x230232878186.jpg)