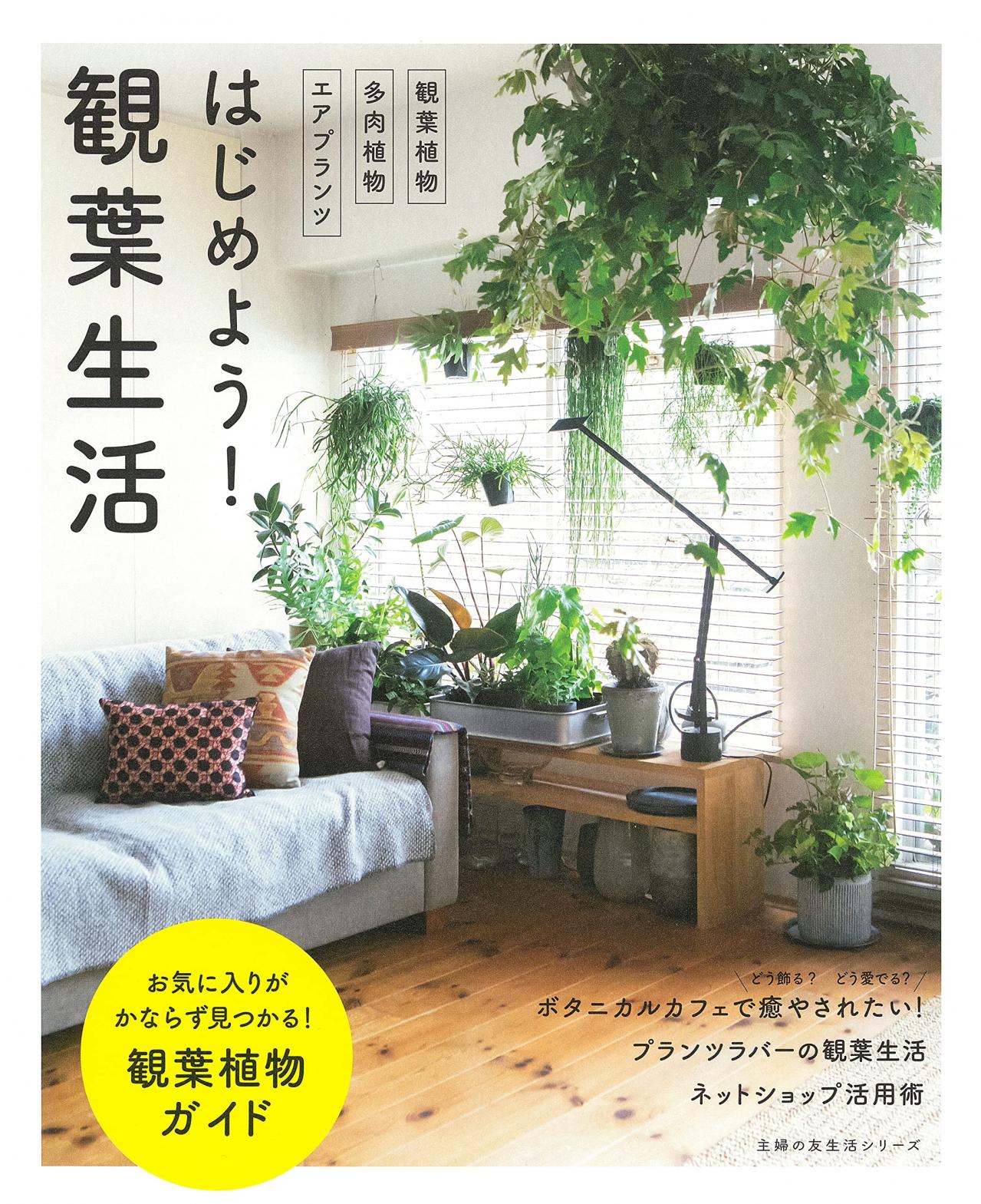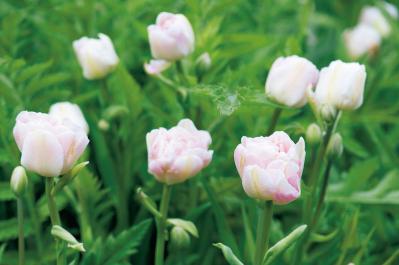【観葉植物の育て方 Q&A】元気がない、葉が落ちた、旅行中は、虫対策、お風呂に置いていい? 18の質問にプロが回答
公開日
更新日
園芸ガイド編集部
虫の困った!
Q 15「室内での虫対策は?」
置き場所や植物の状態など、さまざまな要因で害虫が発生することがあります。観葉植物に発生しやすいのは主にこの3種類です。
<カイガラムシ>植物の樹液を吸い、多発すると植物にダメージを与えるとともに、透明や白い綿状の分泌液を出し、葉をべとつかせ、この樹液を栄養源とするカビが黒いすすのように葉を覆う「すす病」が発生します。
<ハダニ>成虫になると赤茶色になるダニで葉の裏などに寄生します。樹液を吸い、被害が進むと葉の緑色が抜けて、葉面が白っぽくカスリ状になります。
<コナジラミ>白い小さな虫で、葉などをゆらすと飛び交います。被害が進むとハダニ同様に葉の緑色が抜けてしまいます。
これらの防除方法としては、空気の流れをよくするために、換気をこまめに行ったり、霧吹きで葉水をしたり、ふきんで葉面を水拭きするなどしながら、日々チェックを行うことです。葉裏のチェックも忘れずに!
Q 16「虫を発見! どうしよう!」
害虫を見つけたら、まず、ふきんや歯ブラシなどを使って取り除きます。その後、対象害虫に適用のある殺虫剤の散布を行います。室内での散布が厳禁なので、薬剤を使用するときは植物を屋外に移動させてから行います。
また、葉や枝、幹などの表面が黒いすすのようなもので覆われる「すす病」になったら、適用のある殺菌剤を散布します。
カイガラムシ、ハダニ、コナジラミといった吸汁性害虫は小さくても繁殖が旺盛で、短期間で生息数が増えます。早期発見、防除することで被害を最小限に抑えることが大切。一日1〜3回の霧吹きや葉を拭いたりする日々のお手入れが、植物を健やかに育てるポイントです。
Q 17「土からコバエが! どうしたらいい?」
薬剤を使わない場合は、コバエは鉢土の表面に卵を産みつけるため、その部分の土を取り除き、無機質の赤玉土を上からかぶせます。取り除いた土は、卵が孵化しないように殺虫剤をまいて処分します。
Q 18「土にカビが発生! どうしたらいい?」
観葉植物の土には栄養がたくさんあり、水で常に湿っています。高温多湿や日陰、風通しが悪いとカビが繁殖しやすくなってしまいます。カビは見えている以外にも生えている可能性があるので、培養土などの有機堆肥の配合が少ない土に全体を新しくするといいでしょう。
同じ植木鉢を使う場合は、消毒してから使います。プラスチック鉢は水と漂白剤に入れたバケツに浸し、テラコッタは熱湯をかけ、しっかり乾かします。
※この記事は『はじめよう!観葉生活』主婦の友社編(主婦の友社)の内容をWeb掲載のため再編集しています。