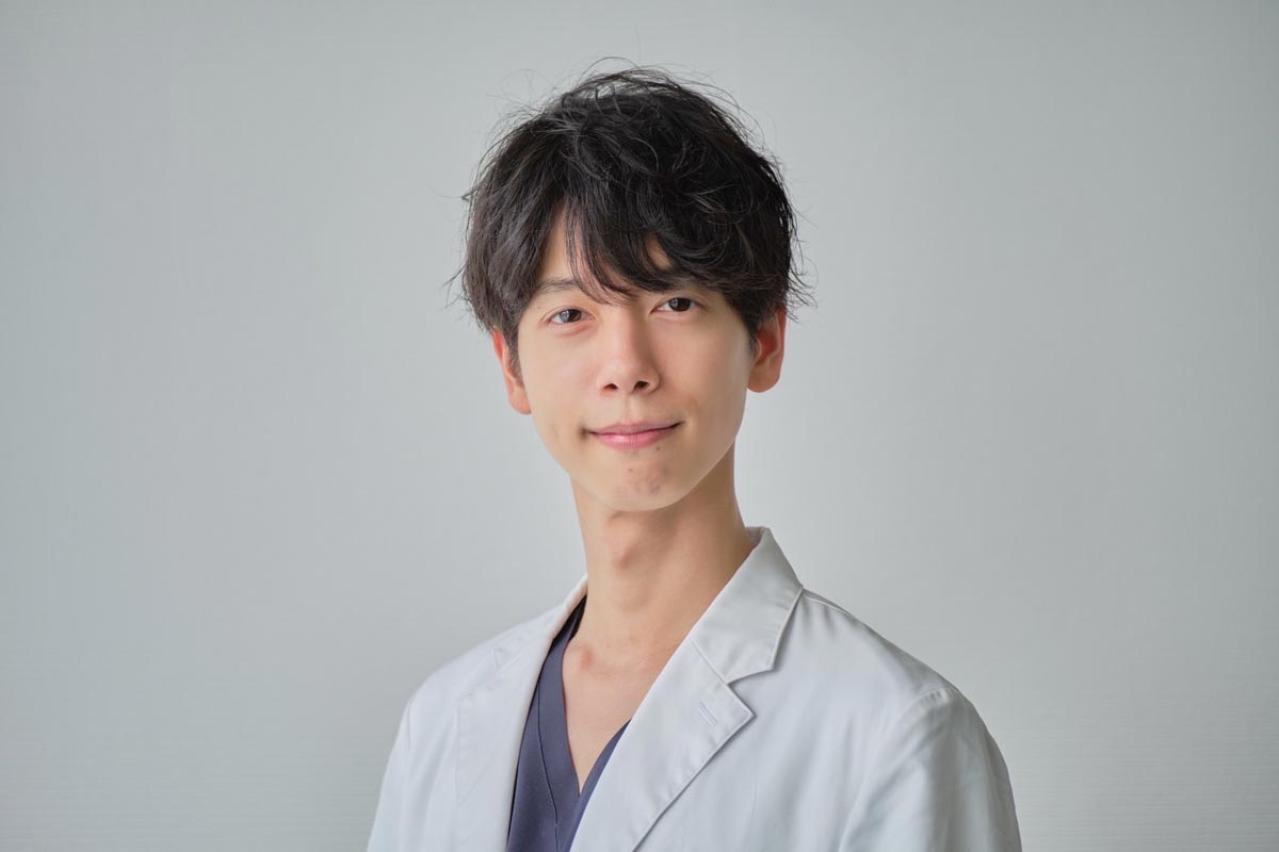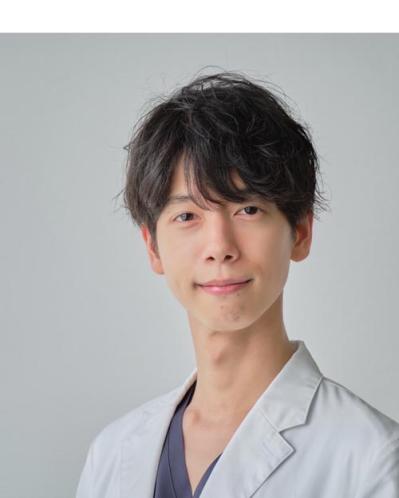「心に”不機嫌さん”はいてもいい」SNSフォロワー12万人 精神科医・藤野智哉さんのアドバイス
怒り・悲しみ・恐れ……自分の中に生まれた“負の感情”に、みなさんはどう対処していますか? SNSフォロワー数12万人の精神科医 藤野智哉さんが、ゆるっとした気持ちで負の感情とつき合える方法を紹介します。新刊『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』から抜粋してお届けする第1回は「不機嫌さんは心にいてもいい」
▼こちらもどうぞ▼
70歳イラストレーター本田葉子さんに学ぶ!「太って見えない」ボーダー着こなし術のポイントいつも機嫌よく見せる必要はないんじゃない?
機嫌がいいに越したことはないけれど、
感情を抑えるのがストレスになるくらいなら
いつもいつも機嫌よく見せる必要はないんじゃない?
「できればいつも機嫌よくいたい」。そう思う人は多いでしょう。
では、「機嫌がいい」とはどういう状態でしょうか。
医学的に「機嫌がいい」という状態が定義されているわけではないのですが、心理学の分野の一つである感情心理学では「気分(mood)」という言葉を使うことがあります。「感情」はその瞬間瞬間の短い揺れ動きですが、「気分」は感情よりも長く続くものとして扱われます。だから「機嫌がいい」というのは、「いい気分が安定して持続していること」ともいえるかもしれません。
いい感情が持続している間は、ほほ笑みが出たり、声のトーンが上がったりもするでしょう。そうした表情や声などさまざまな情報から、周囲の人は「あの人は機嫌がいい」と判断していることになります。
ただ世間では、怒りの感情などネガティブな感情がわかりやすく表出しないことを機嫌のよさとしがちなのではないかと思います。
もちろんまったく怒りが生じない人なんていませんが、その怒りを表出してしまうと機嫌悪く見える、逆に、怒っていても怒りを表出しない人は機嫌よく見える、ということです。本来感情はいろんなサインとして表出されるものなので、怒りだってどうしても漏れ出てしまうわけですが、そうしたサインの出ていないことが機嫌のいい状態とされ、何ならわざとらしくでもハッピー感を出していたらもっと機嫌がいいと思われるわけです。
最近はそうして機嫌よくいることがマナーのようにいわれます。でも僕は、いつもいつも機嫌よくいる必要があるとは思いません。周りの人にとっては、上機嫌が持続してくれているほうがいいに決まっています。でも本来は感情に従うのが動物的であり、怒りが湧いてきたら怒りを出すのが自然なわけです。
人間は社会に適応するため怒りなどを抑えて生きていますが、それが自分にとってストレスになることもあります。本当は腹が立っているのに我慢しなきゃいけないわけですから。
人間なんだから、怒りが湧いたり不機嫌になったりするのは当然。出し方を工夫する必要はありますが、必ずしも他人にとって都合のよい上機嫌をずっと演じる必要はないと思います。