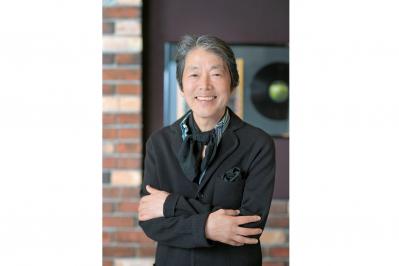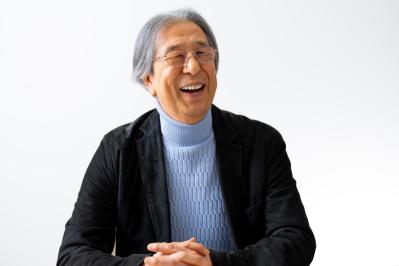【べらぼう】佐野政言(矢本悠馬)は田沼意知(宮沢氷魚)をなぜ斬りつけたのか?
公開日
更新日
鷹橋 忍
斬りかかった理由は?
佐野政言が凶行に及んだ理由には、いくつかの説が存在します。一つ目は「私怨(しえん)説」です。
私怨説には、「佐野の知行地(ちぎょうち)にある佐野大明神という社を、田沼意知が田沼大明神に変えてしまった」、「佐野家の七曜紋入りの旗を意知に貸したところ、『七曜は田沼家の紋だ』と主張し、返却しなかった」、「田沼家はもともと佐野家の家来筋の出なので、昇進の世話を依頼し、合わせて六百二十両もの大金を贈ったのに、昇進が叶わなかった」からなどの他に、「意知から頼まれて佐野家の系図を貸したが、どれほど催促しても返さなかった」というのもあります。
ドラマの第6回「鱗剥がれた『節用集』」で、政言が家系図を手に田沼の屋敷を訪れ、意知に、「田沼家の祖先は、かつて佐野家の末端家臣だった。家系図を改ざんしていいから、その代わりよい役職が欲しい」と告げたというエピソードを彷彿させますね。また第27回でも、政言の父・政豊が「系図を返してほしい」と意次に迫るシーンが描かれていました。
もう一つ、「将軍の鷹狩の際に政言が鴨を一羽、射ち落としたが、射ち落したのは別の者だと意知が言ったため、恩賞から漏れたのを恨んだ」という説もあります。
第27回で、眞島秀和さんが演じる十代将軍・徳川家治の狩りにおいて、「政言の矢で射られた雁(かり)を、意知が隠すのを見た」と、佐野家を訪ねてきた武士に告げられていました。
公憤説と乱心説、陰謀説
私怨説の他に、権勢をふるう田沼意次・意知父子に憤って凶行に及んだとする「公憤(こうふん)説」、幕府評定所(裁判や評議を担う機関)が「佐野政言の乱心による刃傷」と認定したことによる「乱心説」があります。ただし、幕府は厄介な事件などを「乱心」事件として処理することがしばしばあったといいます(藤田覚『田沼意次 御不審を蒙ること、身に覚えなし』)。
また、オランダ商館長・ティチング(1745~1812)は、その主著である『日本風俗図誌』の中で、「この殺人事件に伴ういろいろの事情から推測するに、もっとも幕府の高い位にある高官数名がこの事件にあずかっており、またこの事件を使嗾(しそう=けしかけること)しているように思われる」と記しています。
事件の真相はいまだ明らかではありませんが、ドラマではどのように描かれるのでしょうか。
世直し大明神に祀り上げられる
取り押さえられた佐野政言は、幕府評定所の申し渡しにより、同年4月3日に切腹しています。享年28歳、政言の遺骸は佐野家代々の墓所である徳本寺(とくほんじ/東京都台東区)に葬られました。
この刃傷事件が起きた天明4年は大飢饉に見舞われ、ドラマでも描かれたように米の価格も高騰。人々は苦しみ、田沼政権への不信感を強めていました。ところが、政言が切腹した翌日、あるいは刃傷事件の翌日から、高騰していた米の価格がなぜか下がりはじめたのです。
ドラマと同じように、幕府は以前から米の価格の引き下げに尽力していました。ですので、米の価格が下がったのは、幕府の策の効果がようやく現われたのかもしれません(安藤優一郎『田沼意次 汚名を着せられた改革者』)。
ですが、世間の人々は、これを政言のおかげだとみなしました。人々は政言を「世直し大明神」と祀り上げ、政言の墓所のある徳本寺には人々が殺到。政言の墓所は仏花が溢れ、立ち上る線香の煙に包まれたと伝えられます。
対して、田沼意知の葬列には町人たちが石を投げ、悪口を浴びせたといいます。意知の死は人々の田沼政権への不満があふれ出すきっかけとなり、田沼意次は窮地に陥っていくことになります。
▼あわせて読みたい▼
>>【べらぼう】田沼意次(渡辺謙)が進めている蝦夷地を天領とする計画とは? >>【べらぼう】江戸時代に大ブームが巻き起こった「狂歌」とは? 大田南畝(桐谷健太)はどんな人物? >>【べらぼう】蔦重(横浜流星)が出版した「青本」「往来物」とは?












![【ザ・タイガース】旋風のその先に。別れの裏にあった、知られざる物語[79歳・瞳みのるさんのターニングポイント#2]](/images/articles/thumb20260115vs9fse202645835985.jpg)