【要約小説】名作のあらすじを読もう!
林芙美子の『田舎がえり』あらすじ紹介。旅情あふれる随想と、郷愁を呼び覚ます記憶の旅
公開日
更新日
ゆうゆうtime編集部
林芙美子の『田舎がえり』は、作者の旅路とその中で浮かび上がる郷愁、都会と田舎の対比を描いた文学随想です。一つ一つの描写が、旅人の心の奥に潜む感情を呼び起こします。
▼他の要約小説も読む▼
>>【要約小説】名作のあらすじを読もう!小説特集鉄道の旅と出会い
物語の始まりは東京駅の混雑したホーム。主人公が三等寝台車で出会う人々の様子が描かれます。隣の寝台には泣いている様子の娘、上の階にはサスペンダーが垂れ下がった旅人。非日常と孤独が交錯する夜の車内で、疲弊した日常を忘れようとする姿が印象的です。熱海、大垣と移動を続けながら、周囲の旅人たちとの微細な交流が主人公の内面を映し出します。
京都の情景と宿
京都に降り立った主人公。人力車が並ぶ駅前や、風情あふれる宿「西竹」での滞在描写は、旅情をかき立てます。宿の狭いながらも工夫の施された屋上庭園や、そっと置かれた植木鉢は、京都の風流を表しています。滞在先では啄木歌集を前に沈思しながら、人間の営みや自然、文化の美しさに思いをはせます。
山科の風景と古都の暮らし
次の目的地は山科。どこまでも続く疎水のほとりを歩き、地元の人々の普通の暮らしに触れる場面では、都会とは異なるゆったりとした時間が流れていることを強く感じます。赤松越しに見える電車や、時折通る屋形船の描写を通じて、何気ない風景が煌(きら)めく瞬間として丁寧に描かれます。その一方で、大石内蔵助ゆかりの家では暗い室内が過去を振り返らせ、深い感慨を呼び起こします。
尾道の記憶と再会
尾道への旅では、幼き日の記憶が次々とよみがえります。変わりゆく町並みに驚きつつも、魚臭さや波の音が昔を思い出させ、胸が熱くなる主人公。旧友との再会や、昔過ごした海の近くの旅館での宿泊が、田舎での懐かしさと共に、失われた時への愛惜を感じさせます。思いも寄らぬほど時を過ごした尾道は、まさに彼の心に眠っていた「ふるさと」そのものでした。
因島の訪問で得た郷愁
さらに船で向かった因島でのエピソードでは、都会の喧騒とは対極にある田舎暮らしの一日が描かれます。親戚との再会、田舎の味覚、子供たちとの交流。これらはすべて、都市部での生活に疲弊した主人公にとって安らぎをもたらすものでした。海の静けさや自然の豊かさが、都会生活では得られない安堵(あんど)感を象徴しています。
帰路と完成された人形
旅の最後には、京都から持ち帰る人形を巡るエピソードが語られます。人形は何ヶ月もかけて完成され、美術品としての一面だけでなく、郷愁の象徴とも言える存在。帰りの列車では、寝台に人形が横たわっていたという独特なエピソードも、物語にユーモアを添えています。
まとめ
林芙美子の『田舎がえり』は、旅を通して記憶や場所に宿る郷愁を丹念に描き出した名作です。都会の喧騒を離れ、田舎の風景や人々との交流に浸る主人公の姿は、読者に穏やかで温かな共感を引き出します。それは現代の私たちにも通じる「帰りたい場所」「大切な記憶」を呼び起こす物語。丁寧な描写と言葉選びから、土地や時間への愛情がにじみ出ます。日常を離れて、どこか懐かしい場所への思いを共感してみてください。
▼あわせて読みたい▼
>>樋口一葉の『琴の音』あらすじ紹介。音楽による心の救済。愛と葛藤の物語 >>福沢諭吉『学校の説』あらすじ紹介。教育と革新、そして学校のあるべき姿とは? >>【戦後80年に読みたい小説】二葉亭四迷の『未亡人と人道問題』あらすじ紹介。戦争で夫を亡くした女性の再婚、そして新たな価値観
※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。
▼関連書籍を読む▼
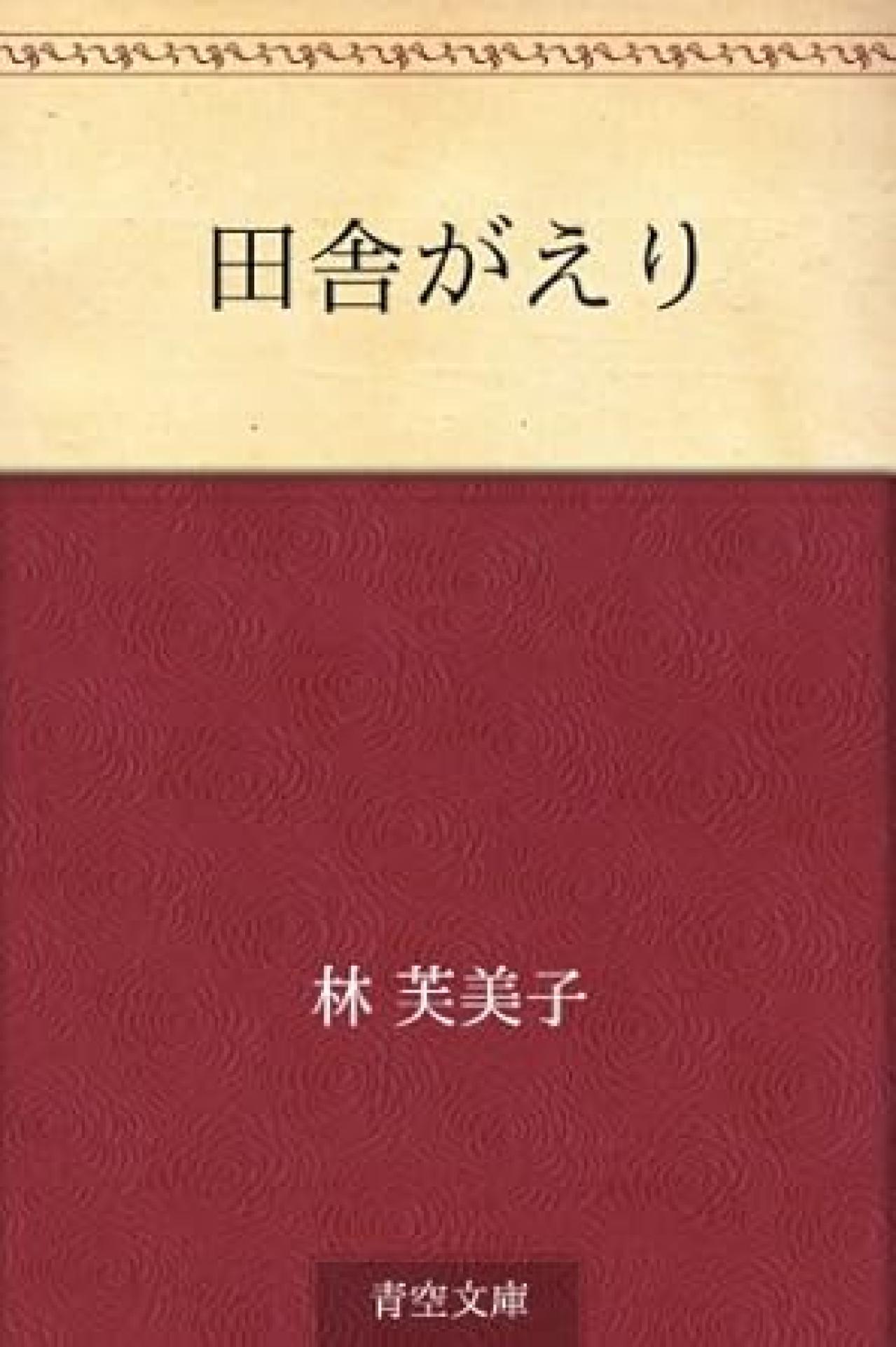
田舎がえり
林芙美子(著)
青空文庫(刊)
※詳細は以下のボタンへ






















