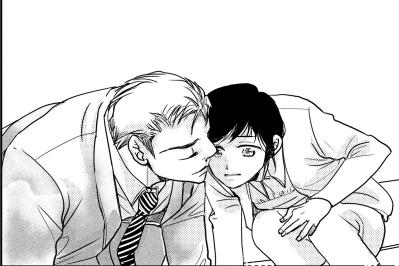さだまさしさん、母を語る。「お前を信頼しています 母より」手紙の最後には、いつもこの言葉がありました
公開日
更新日
ゆうゆう編集部
いくつになっても母の存在は大きいものです。今も心に刻まれている、母が教えてくれたことを、さだまさしさんに語っていただきました。明るくて歌が好き。愚痴を言う姿は一度も見たことがなかった。困ったときは「あんたは大丈夫」と。そんな言葉が心強かったそうです。
3歳からヴァイオリンの 英才教育がスタート
「幼少期から僕の音楽の才能を信じて疑わなかったのが母。よくぞそんな勇気があったと思いますけど」
さだまさしさんは懐かしむような目でそう言い、嬉しそうに笑った。
さださんの母・喜代子さんは1926年、長崎県長崎市生まれ。10代の多感な時期を戦争という動乱の中で過ごし、終戦後、材木商として働く雅人さんと結婚した。そして夫婦の間に長男として生まれたのが、さださん。若い頃から音楽が好きだった母は、さださんが3歳になるとヴァイオリンを習わせ始めた。
「ヴァイオリンに関しては、母はとにかくうっとうしかったです(笑)。母は大人だから、先生の言うことを最初に理解して僕に伝えるんだけど、母自身は何もできない。実際に弾くのは僕だけれど、それが正しいかどうか母にはジャッジできない……。母が言うことと先生が言うことをすり合わせて、自分で想像しながらやっていく苦労がありました。とはいえ、僕は素直な子どもだったので、どうにか親や先生の期待に応えようと一生懸命やっていましたね」
楽器や楽譜の購入費用にレッスン代、ヴァイオリンを習うにはお金がかかる。そこにきて、父の商売が徐々に傾き始めた。
「結局、商売下手な父は材木屋を潰してしまい、僕が小学2年生のときから長屋暮らしになりました。お金も自由にならず大変だったと思いますが、それでも母は僕の音楽の才能を信じてくれていたように思います。ヴァイオリンの先生から『この子は才能がある』と言われたから、僕を一人前のヴァイオリン弾きに育てれば自分が親になったかいがあると思ったのかな。あるいは、人が追い込まれると何かにすがるように、母にとってはすがる対象が僕のヴァイオリンだったのかもしれません」
苦境にあっても希望を失うことなく、母は常に前向きだった。
「母の兄弟姉妹も茶目っけがあったり、明るいところはありましたけれども、母は混じりけなく明るかった。そして歌が好きでね。友達にお米を借りに行くときでも、親類にお金を借りに行くときでも、僕と弟、妹の手を引いて、歌を歌いながら遠足がてら出かけていました。すごく苦労しているはずなのに、眉間にシワ寄せて愚痴ばっかり言っているような姿は一度も見たことがありません」
中学生からひとり暮らし。 母の信頼を裏切り……
気丈に振る舞う母を間近で見ていたさださんの心には、子どもながらに「母に苦労をさせたくない」という思いが芽生えた。買い物をしているときに母の財布の中をのぞき見していたので、「何が食べたい?」と聞かれると「うどん」。うどんがいちばん安上がりだと知っていたから。
「弟が『肉を食べたい』なんて言うと、僕は『いや、絶対うどんがいい』。弟にタックルして、弟の意見を押しつぶしていました(笑)。僕は早く大人になりたいと思っていたんです。何も根拠はないけれど、大人になったらお金のことで母に苦労させないという自信がありました。まあ、そう言いながら実際には大人になって映画つくって借金して、結局は母に心配かけましたけどね(笑)。でも母は借金に慣れていますから、そのときも全然うろたえませんでした」
小学5、6年生のときには学生音楽コンクールの西部大会で入賞。ヴァイオリニストとしての将来を期待されたさださんは、中学生になると本格的なレッスンを受けるために単身上京し、下宿生活を始めた。
「ひとり暮らしになって、母の目が消えたことで、ちょっとぐらいとサボり始めるわけです。その『ちょっとぐらい』がヴァイオリニストにとっては致命的。どんどん下手になっていくのが自分でもわかりました」
そんな息子の暮らしぶりを見透かすかのように、長崎の母からは週に一度、手紙が届いた。
「家族のことや長崎のことなどが書いてあって、最後に一行、『お前を信頼しています 母より』。毎回この言葉が必ず書いてありました。これはけっこう重たかったですよ。それでも母は本当に僕のことを信頼してくれていたみたいで、たとえば学校に電話して『うちの子はどうでしょうか』とか、下宿に電話をして『真面目にやっていますか』とか聞いたことは一度もなかったようです」
中学卒業を目前に都立の音楽高校を受験するも、学科試験に失敗。私立の國學院高校に進学した。
「高校生活は楽しかったけれど、僕が目指す芸大に行くためにはピアノも習わなきゃいけない。そのためにはお金がいるし、安いヴァイオリンしか持っていなかったからコンクールではとても通らないし……。そうなってくるとだんだんに門が狭くなり、道が細くなり、道のりは遠くなり。高校3年生のとき、ついにヴァイオリニストの道を諦めました」
ヴァイオリンをやめる─。決心したものの母には言い出せなかった。
「父に話したら『お前の人生だから自由に生きていけばいいけれども、お母さんはショックを受けるだろう。折を見て俺が話すから、今は言わないでおきなさい』と言われましたが、結局、父は母には言っちゃいなかった。それでも母はだんだんにわかったんじゃないかな。僕がヴァイオリンに熱心でなくなったのは見ていたらわかるし、芸大を受験せず國學院大学に進んだし。そのときに母は諦めたんだろうと思います」