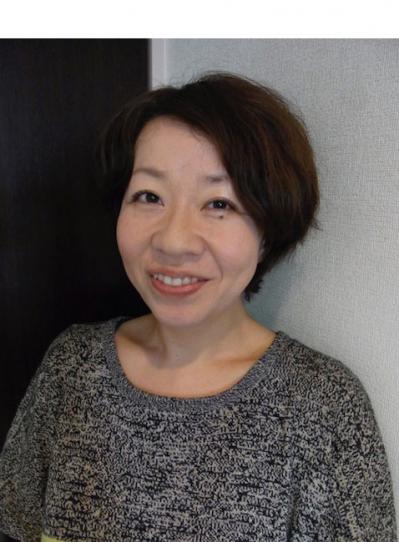朝ドラ【あんぱん】を見て、戦争と平和を想う。現実のニュースとドラマが重なり、やるせなさが心を包む
公開日
更新日
田幸和歌子
1日の楽しみは、朝ドラから! 数々のドラマコラム執筆を手がけている、エンタメライター田幸和歌子さんに、NHK連続テレビ小説、通称朝ドラの楽しみ方を毎週、語っていただきます。漫画家のやなせたかしさんと妻の小松暢さんをモデルに、激動の時代を生き抜く夫婦の姿を描く物語「あんぱん」で、より深く、朝ドラの世界へ!
※ネタバレにご注意ください
▼前回はこちら▼
戦争と平和についてのリアリティを痛感する中での放送となった
現在放送中の今田美桜主演のNHK連続テレビ小説『あんぱん』は、ヒロインの夫が『アンパンマン』の作者・やなせたかしをモデルとしたものであることは説明の必要はないだろう。やなせたかしは多くの童話やエッセイ、そして歌詞などに、「生」そして「正義」というものに対するメッセージを残してきた。
本作でも「正義は逆転」するという観点のもと、嵩(北村匠海)が直面するさまざまな不条理が描かれ、視聴者に正義とはその立場や考え方、社会の空気などによって簡単に真逆のものとなる概念であることを強く印象づけてきた。
そんななか放送された第12週のサブタイトルは「逆転しない正義」。これまでと真逆のスタンスが突きつけられた。舞台は前週に引き続き激化の一途を辿る戦況となる。奇しくもイランとイスラエルが交戦状態に突入し、連日その様子が報じられることで戦争と平和についてのリアリティを痛感する中での放送となった。
中国福建省に上陸した小倉連隊の中で、嵩はその絵の才能が買われ宣撫班に配属され、現地の市民たちに向けたある種の広報、啓蒙活動を紙芝居によって行うことになる。これは当時の日本から見た中国へのスタンス、広報というよりもある意味での洗脳に近いものだったであろう。
そもそも「宣撫」とは何なのだろうか。やなせたかしの著書、『ぼくは戦争はだいきらい ~やなせたかしの平和への思い~』にも、この「宣撫」について、占領下の現地人たちに日本のことを知ってもらい怖くないよとアピールする宣伝活動のことだと記している。
嵩は父・清(二宮和也)の手帳に書かれていた「東亜の存立と日支友好は双生の関係だ」という言葉をもとに、『双子の島』という友好の思いを込めた物語を創作する。紙芝居は笑いに包まれ好評を得た。やなせの著書にもこのエピソードは登場するが、作中で描かれた通り、通訳が日本軍の悪口を中国語で言っていたのではないかと振り返っていた。
「空腹は人を変えてしまう……」
昭和20(1945)年3月10日、東京大空襲。日本の敗戦はほぼ決定的なものとなり、嵩たちの駐屯地は敵の大攻撃を受け孤立、もはや宣撫どころではなく嵩は元の分隊に戻されることとなった。補給路が絶たれ、空腹が生きるための最大の敵となって立ちはだかることとなってしまった。
飢えは「正義とは何か」を考える隙も与えず生を奪っていく。空腹のあまり朦朧とした康太(櫻井健人)は民家に押し入り民間人である中国人の老婆(天野眞由美)に銃を向け食べ物を要求する。辛いのは、この民家はすでに別の日本兵に襲われており、鍋の中もすべて空っぽとなった状況であったことだ。空腹、そしてそもそもの戦争の理不尽さを痛感する演出である。
そんななかでも産みたての卵を茹で彼らに老婆は差し出す。殻をむくことすら待てずにそのまま丸かぶりするさまは、真に迫る演技といっていいだろう。それを傍で無気力な表情で無言で見つめる嵩にも、老婆は卵を差し出し食べるようすすめる。
「謝謝……おいしい……」
感謝の涙を流しながら、嵩も殻ごと卵をむさぼる。
「空腹は人を変えてしまう……」
嵩たちの姿を見つめながら老婆はそうつぶやいた。卵を食べ涙を流した嵩が感じたこと、それこそまさに、アニメ『それいけ!アンパンマン』の歌詞にある「生きる喜び」そのものといっていいのだろう。
亡くなった伯父の寛(竹野内豊)が何度となく嵩たちに伝えてきた、「何のために生まれて、何をしながら生きるがか」という言葉が、生の危機に直面したことでより強く響きわたるかのようだ。