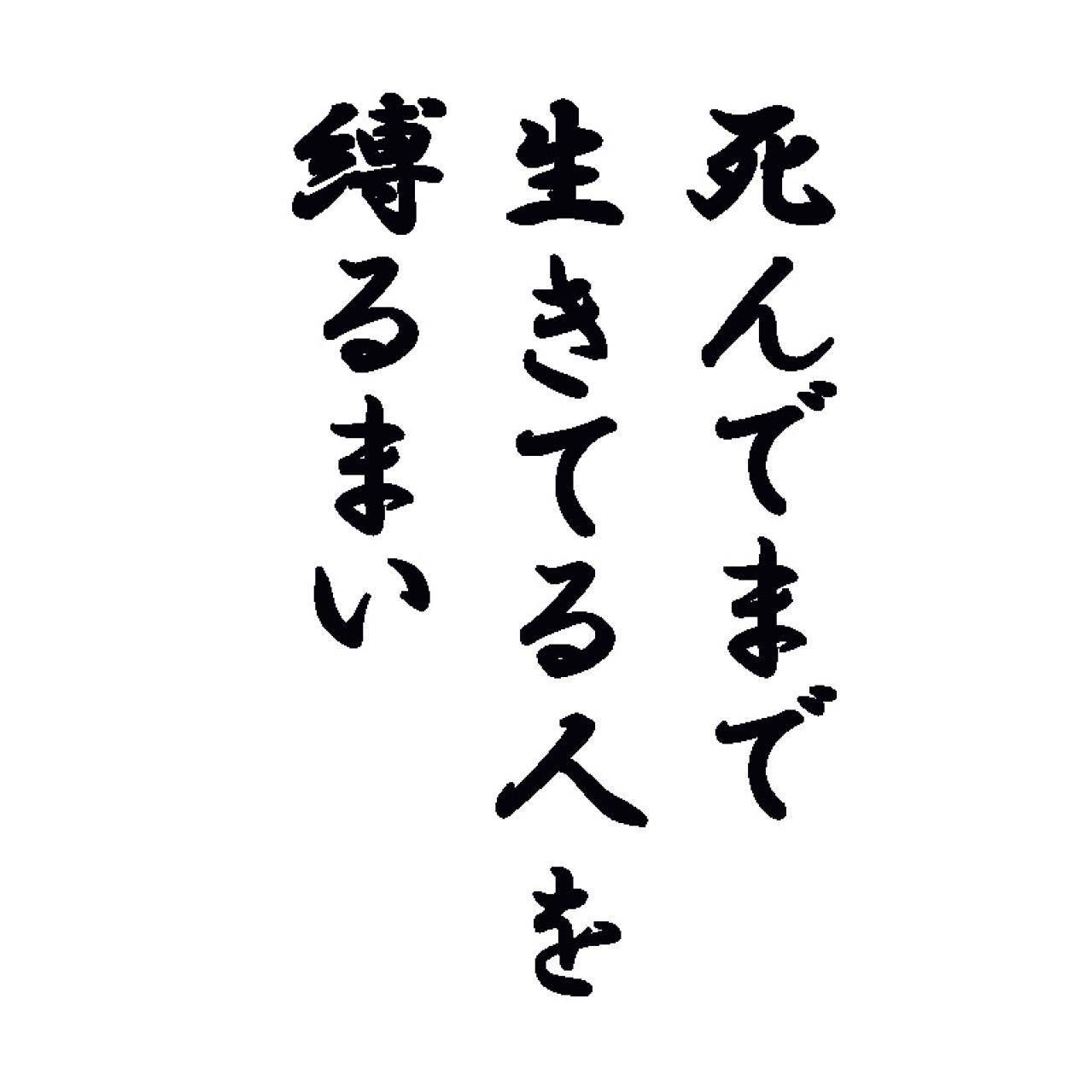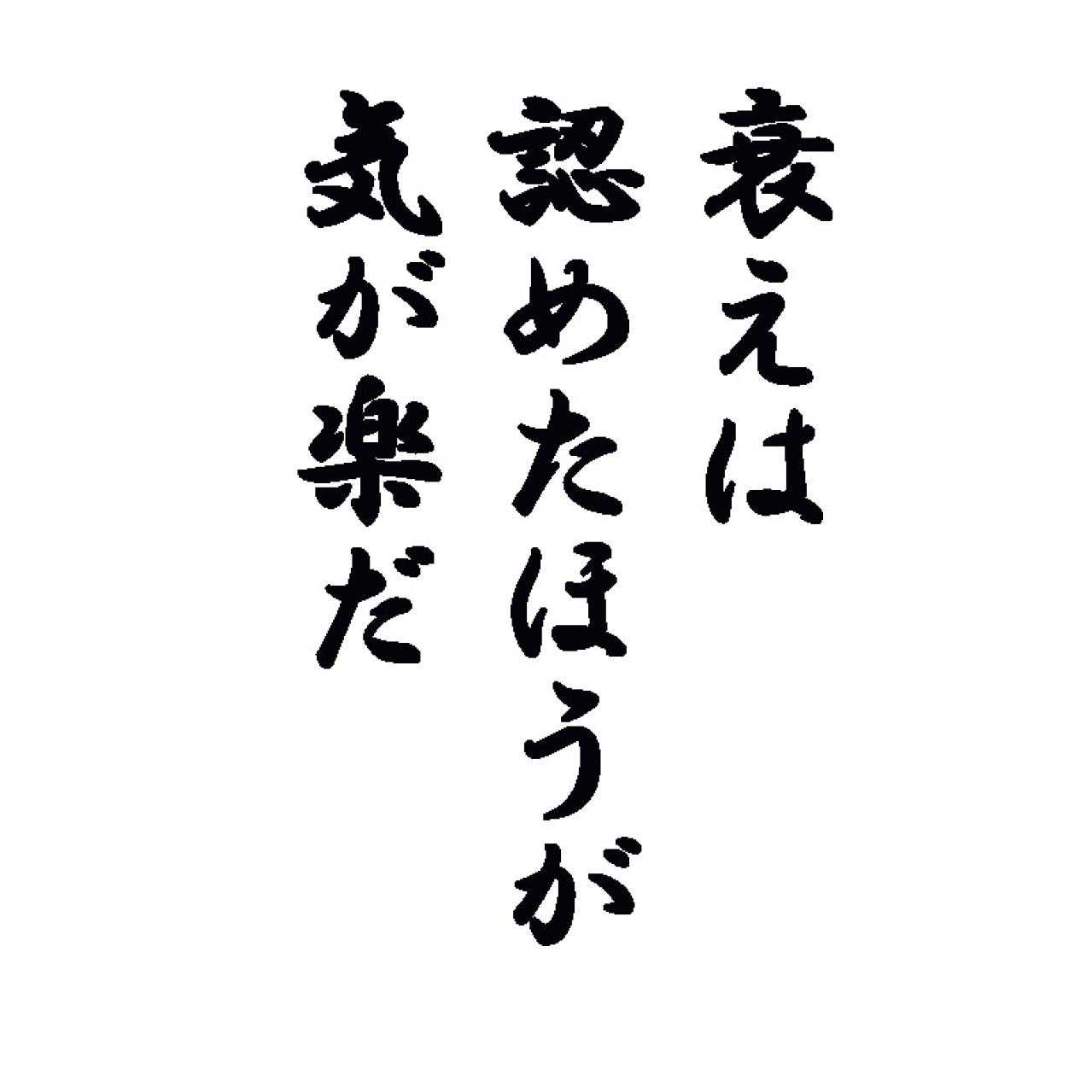【和田秀樹さん】「最終的に元気で長生きできる人の条件は…」高齢期に入る前に知りたい「終活」の心構え
年金生活に入る頃から、気になり始めるいわゆる「終活」。いつの間にか増えてしまった大量の持ち物を整理したり、生活を縮小したり、あるいは遺言をしたため、エンディングノートを作ったり。そうした準備は必要だよ、という人がいる一方、いやいやそんなものは不要だよという人も。老年精神科医の和田秀樹さんは後者。なぜ「終活」は要らないのか、その考えを全6回でご紹介します。今回は第3回です。
▼前回はこちら▼
≫≫第2回【和田秀樹さん】「高齢女性こそ恋せよ!」医学的にも判明しているそのメカニズム
和田秀樹さん 精神科医
わだ・ひでき●精神科医。1960年大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。高齢者専門の精神科医として35年以上にわたり医療の現場に携わっている。『80歳の壁』『70歳の正解』『逃げ上手は生き方上手』『どうせ死ぬんだから 好きなことだけやって寿命を使いきる』『女80歳の壁』など著書多数。
遺された人のことなんて考えなくていい!
遺された人のことなんて考えずに、好きなことを思いっ切り楽しんでいれば終活なんていらない!と言う和田秀樹さんからのアドバイスです
死んでまで 生きてる人を 縛るまい
「世間の常識」や、そこから生まれた「思い込み」も、幸・不幸を分ける原因に。例えば、お墓の問題がそれだ。生前にお墓を用意したり、子どもにお墓の代金として数百万を残したりする人もいるが、この行為には「私が亡くなった後、家族にはお墓参りに来てほしい」という気持ちが含まれている。この気持ちは理解できるものの、自身は反対だと和田さんは言う。
「子孫を将来にわたり縛る足かせになりかねないと思うからです。私だったら、それは彼らに強要するように思うのでしたくないですね。そうは言いながらも私自身はご先祖様には感謝していますし、盆暮れには手を合わせますが、若い世代にそれを強要はしたくない。『死んだら関係は切れる』と思っていれば、誰にも気を遣わずに、自分の好きなように生き、お金を使うこともできます。そのほうが有意義だと思います」
衰えは 認めたほうが 気が楽だ
人はいつか死ぬ、ということは、頭では理解できていても、なかなか受け入れられない。そこで和田さんが提案するのが「老いの2部制」だ。人生自体も「2部制」で受け止めたほうがよいと本文で書いたが、老いの時期も前半と後半に分けて考え受け入れやすくするのだ。
「前半は『老いと闘う時期』。70代中頃~80代前半の人が相当します。後半は『老いを受け入れる時期』で、80代中頃~90代の人が当たります。前半は衰えてくる体の機能をできるだけ衰えさせないよう『現状維持』を心がける時期。運動機能や脳の機能は、放っておけばどんどん低下します。しかし、元気なうちに維持するよう心がければ、低下の速度は緩やかになるのです。そして大事になるのが、後半への上手な切り替えです。うまく受け入れられると、『できなくなったこと』より『できること』に目を向けられるようになる。こういう人が最終的に元気で長生きできるのです」