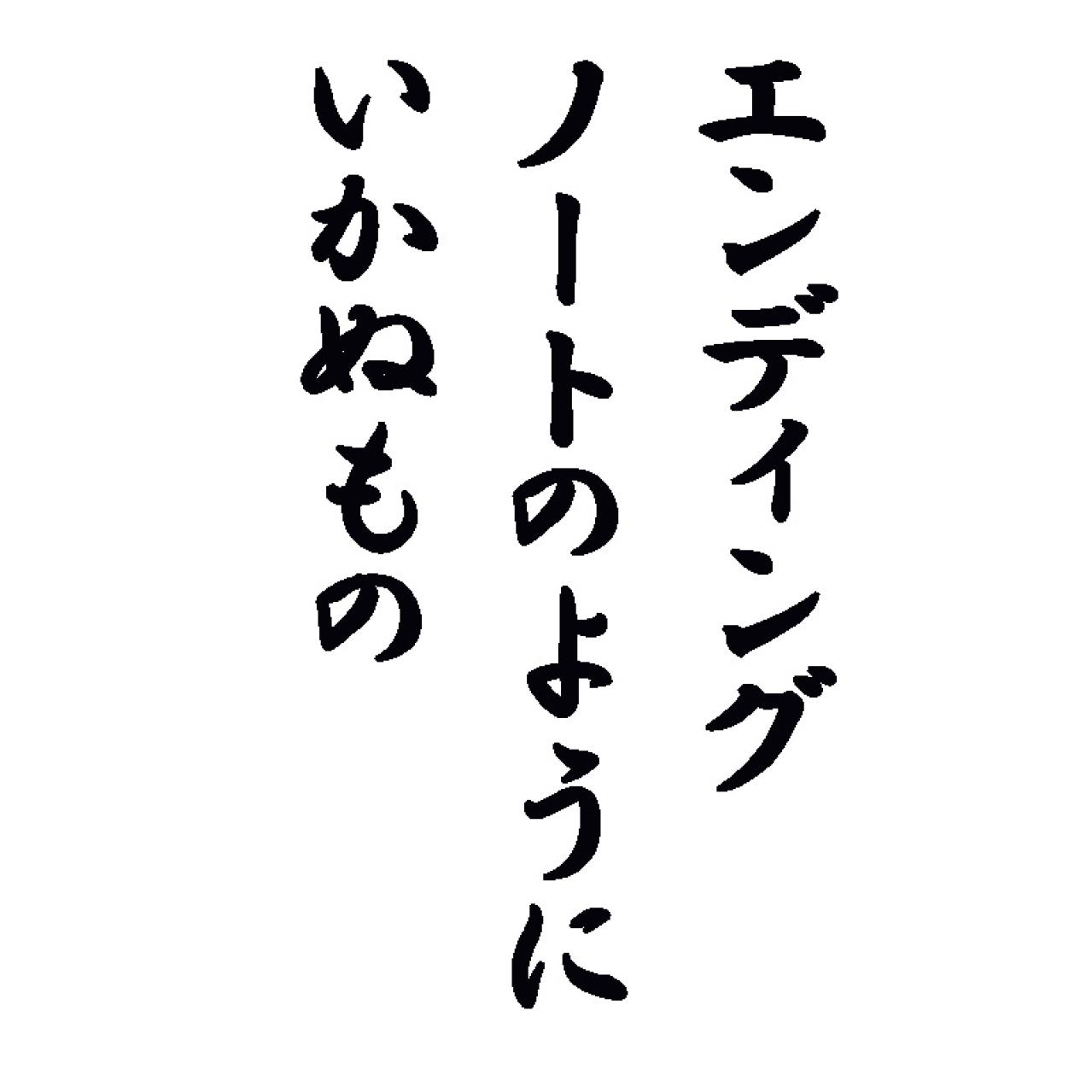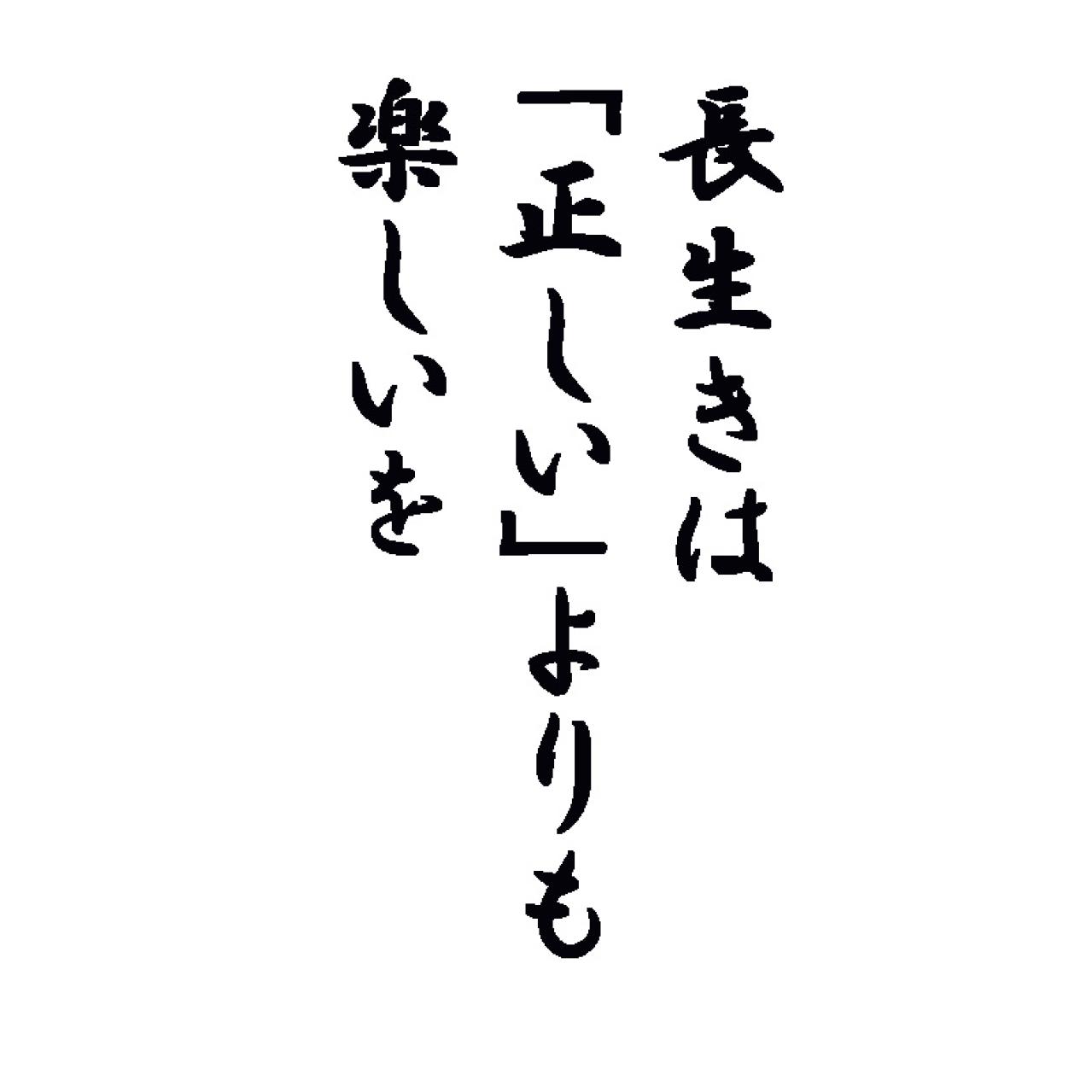【和田秀樹さん】「最終的に元気で長生きできる人の条件は…」高齢期に入る前に知りたい「終活」の心構え
高齢期における医療との付き合い方
エンディングノートのように いかぬもの
「終末期医療」についてどう考えるかということも、「終活」の大事なテーマの一つ。医療による延命治療をせず、自然に死を迎える「尊厳死」を選びたいと書き記す人もいるはずだ。だが、このこと自体は否定しないが、しかし和田さんは、そこに医療のインチキさも感じる。
「なぜかというと、最期のときには『人間の尊厳を保つ』と言って医療を控えるのに、その手前の段階では『人間の尊厳を無視した医療』を行っているからです。例えば70歳で血圧が高い人に、医師は血圧の薬を飲み、塩分を控え、お酒もやめるように指示します。患者さんは、そこから十数年、食事もお酒も我慢して生きるわけです。これは我慢して生きることを強制された延命治療といえます。それで寿命が延びるかどうかは医師だってわかっていません。その不確かな医療のために楽しいはずの晩年をつまらないものにしている。これは人間の尊厳を踏みにじる医療だと私は思います」。本当に尊厳を保ちたいなら、「幸齢期」の積極的な医療も控えるべきだと和田さんは強く主張する。
長生きは “正しい”よりも 楽しいを
日本は今や「がんで死ぬ国」になった。そのがんを撃退するには免疫力を上げなければいけない。それだというのに、肉も塩分もお酒もタバコもダメ、となったら生きる楽しみが奪われて、むしろ免疫力は下がってしまう。確かに味の濃い食事も、お酒もタバコも心臓病のリスクを上げる「負の一面」はある。しかし同時に幸福感を高めて免疫力を上げるという「正の一面もある。つまり極端に言えば「医師の指示を聞いてがんで死ぬ」か、「好きに生きて心臓病で死ぬ」かの選択になってくる。それはひいては、「医者の言うことを聞いて、わずかに長き生きする」か、「好きに生きて、わずかに早死する」かということでもある。いずれにしても大規模比較調査をしたことがない日本では「不完全な情報」でしかない。
「それなら『好きに生きるほうがいいのでは?』というのが、私の提案です。私の35年の診療経験からも、節制してしょぼくれて生きている人より、好きに生きている人のほうが、元気に長生きしているのです」
撮影/佐山裕子(主婦の友社) 取材・文/志賀佳織 イラスト/ピクスタ
※この記事は「ゆうゆう」2025年5月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のため再編集しています。
▼あわせて読みたい▼