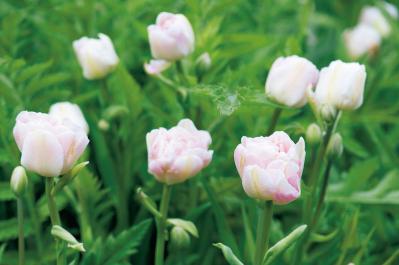【ガーデニング】気温20℃が注意信号!苦手な病害虫に備えよう
公開日
更新日
光武俊子
【黒星病】マルチングで泥ハネを防ぐ
葉に黒い斑点ができて、次第に全体に広がり、葉が黄変して枯れ落ちます。病気が進行すると株の葉がすべて落ちてしまうことも。気温20~25℃になる初夏や秋によく発症します。雨が多く気温が低めの梅雨時はとくに注意が必要。土壌や枯葉に潜む菌が泥ハネで植物に付着して発症します。
バラ栽培では避けられないほど発症率の高い病気です。バラ以外のバラ科のゲウムやコデマリ、ウメやイチゴなどにもよく出ます。葉がすべて落ちてしまっても枯死するとは限りませんが、体力が落ちてしまうので、できるだけ葉を残すよう努めましょう。バラは3~5月、7~9月、冬の剪定後に薬剤散布を月1~2回。
鉢植えの水やりは株元に静かに注ぎ、庭植えでは株元にグラウンドカバープランツを植えたり腐葉土などでマルチングをしましょう。根をしっかり張らせて株を元気に育てることで、病気を寄せつけにくくなります。窒素分の過多や、肥料不足の両方に注意します。
【ハダニ】葉裏によく水をかける
葉っぱがかすれたように薄くなって変色していく様子は、病気と間違うかもしれません。けれども、虫眼鏡などでよく見ると葉裏にごく小さな赤い虫がいます。雨の当たらないベランダや室内栽培で目立ち、大量発生すると糸を張って葉や花を丸ごと覆ってしまいます。
3~10月、とくに梅雨明け~9月ごろが発生のピーク。高温で乾燥した条件を好むので、雨に当たらない場所の鉢植えは葉裏など全体に水を念入りにかけて、洗い流します。ハダニ対策には専用の薬剤がありますが、繰り返し使うと耐性ができやすく、対策しにくい害虫です。
株間を十分に開けて、風通しよい環境をつくって、ハダニを近づきにくくしましょう。ハダニはクモの一種ですが、クモはハダニを食べてくれます。私は室内でみつけたクモは必ずつかまえてベランダに放します。まあ、気休めですが……。
【アブラムシ】刷毛でこそぎ落とそう
茎葉や新芽、蕾など、柔らかくていかにもおいしそうな部位に大量発生します。ほんの数ミリの小さな虫でも大量に発生して体液を吸われると、茎葉は変形。さらに、アブラムシの排泄物は甘くてアリが集まったりカビが発生しやすくて、すす病などのウイルス病が入り込むこともあるので、注意が必要です。
私は指で茎を挟んでボロボロと捕殺することが多いですが、花苗の生産者さんは刷毛で払い落とすとおっしゃっていました。落としたアブラムシはまた這い上がってくるので、新聞紙などを株元に敷いておいて一網打尽にするそうです。また、黄色いものに集まる習性を利用した捕獲シートも販売されています。
アブラムシはほぼ一年中発生しますが、とくに春と秋の雨が少ない時期がピーク。暑さには弱くて、真夏日になると数が減りますが、秋には戻ってくるので要注意。日ごろから下草を生やしてテントウムシが生息しやすい環境を整えて、アブラムシを捕食してもらう手もあります。