【要約小説】名作のあらすじを読もう!
与謝野晶子の『教育の民主主義化を要求す』あらすじ紹介。教育に民の声を届ける改革論とは?
公開日
更新日
ゆうゆうtime編集部
与謝野晶子による『教育の民主主義化を要求す』は、日本の教育制度改革を説いた革新的なエッセイです。熱き提言と未来への希望が描き出される、その内容に迫ります。
官僚支配から国民の手へ――教育改革の第一歩
筆者である与謝野晶子は、当時の文部大臣に向け教育改革の提言を行っています。彼女は、国民から隔離され孤立する教育制度に警鐘を鳴らし、それを「民主主義化」する必要を強調します。具体的には、教育を一部の特権階級や官僚の管理から解放し、地域の父母、有権者からなる教育委員会を組織することを提案しています。そして、教育を単なる制度的なものではなく、国民が主体的に関与できる「生活の場」として再構築すべきだと主張します。この考えは、現代においても教育現場で親や地域が参加する理想の姿に重なる部分がありますね。
国語教育の再編――口語体を主軸に
次に晶子が語るのは、国語教育のあり方です。彼女は、「国語は国民が意志を表現する手段である」と断言し、その効率化を目指すべきだと述べます。特に、時代遅れの文章語教育を批判し、全て口語体に統一することで子どもたちが言語を自然に習得できる環境作りを提案しています。現代では昔よりも使いやすい教材や、デジタルツールが生まれていますが、このような「子どもの負担を減らしつつ、実用性を高める教育」の視点は今なお重要です。
教科書の質を問う――文学と教育の融合
そして、現代の国語教科書についての批判が続きます。晶子は、教科書に記載された文章が、現代語として質が低く、魅力に乏しいものだと指摘します。本来ならば、日本文学の優れた口語体で執筆した作品を活用し、国民全体の感性や文化の質を高めるべきと論じています。また、詩や唱歌が教育の一環として使われるべきだとしつつも、国語教科書には芸術的価値の高い作品をもっと含めるべきだとも提案しています。こうして教育と文化を一体化して考える視点は、現代社会においてますます求められています。
官僚と文学者の距離
さらに、文部省が学者を中心とした狭い視野で教科書を編さんしていることを問題視します。晶子は、詩人や作家といった現代文学の担い手をもっと積極的に教育現場に関わらせるべきだと訴えています。当時としては画期的な提案ではないでしょうか。教育がリアルタイムで文化と融合することで、より生き生きとした学びの場が生まれるという視点も示されていますね。
まとめ
与謝野晶子による『教育の民主主義化を要求す』は、教育制度の抜本的な改革と、教育現場に文化や国民のニーズを反映させる必要性を訴えたエッセイです。官僚の独断で進められていた冷淡な教育から解放し、父母や地域といった現場に密接に関わる人々の参加を提案。そして、子どもたちがより身近に感じる国語教育や、現代文学の力を借りた教科書編集の重要性を論じています。本作は教育のみならず、文学や文化のあり方についても深く問いかけた作品です。いまも変わらぬ教育論題にも響く内容であり、この提言が持つ普遍性に驚かされます。ぜひ大人の視点から、その意義を読み解いてみてください。
▼あわせて読みたい▼
>>魯迅の『端午節』あらすじ紹介。「大差ない」という思想が現代に問いかけるもの >>若山牧水の『姉妹』あらすじ紹介。お米と千代が抱える運命と葛藤を描いた物語 >>吉川英治の『かんかん虫は唄う』あらすじ紹介。貧困と希望の交差点で生きる少年の旅路
※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。
▼関連書籍を読む▼
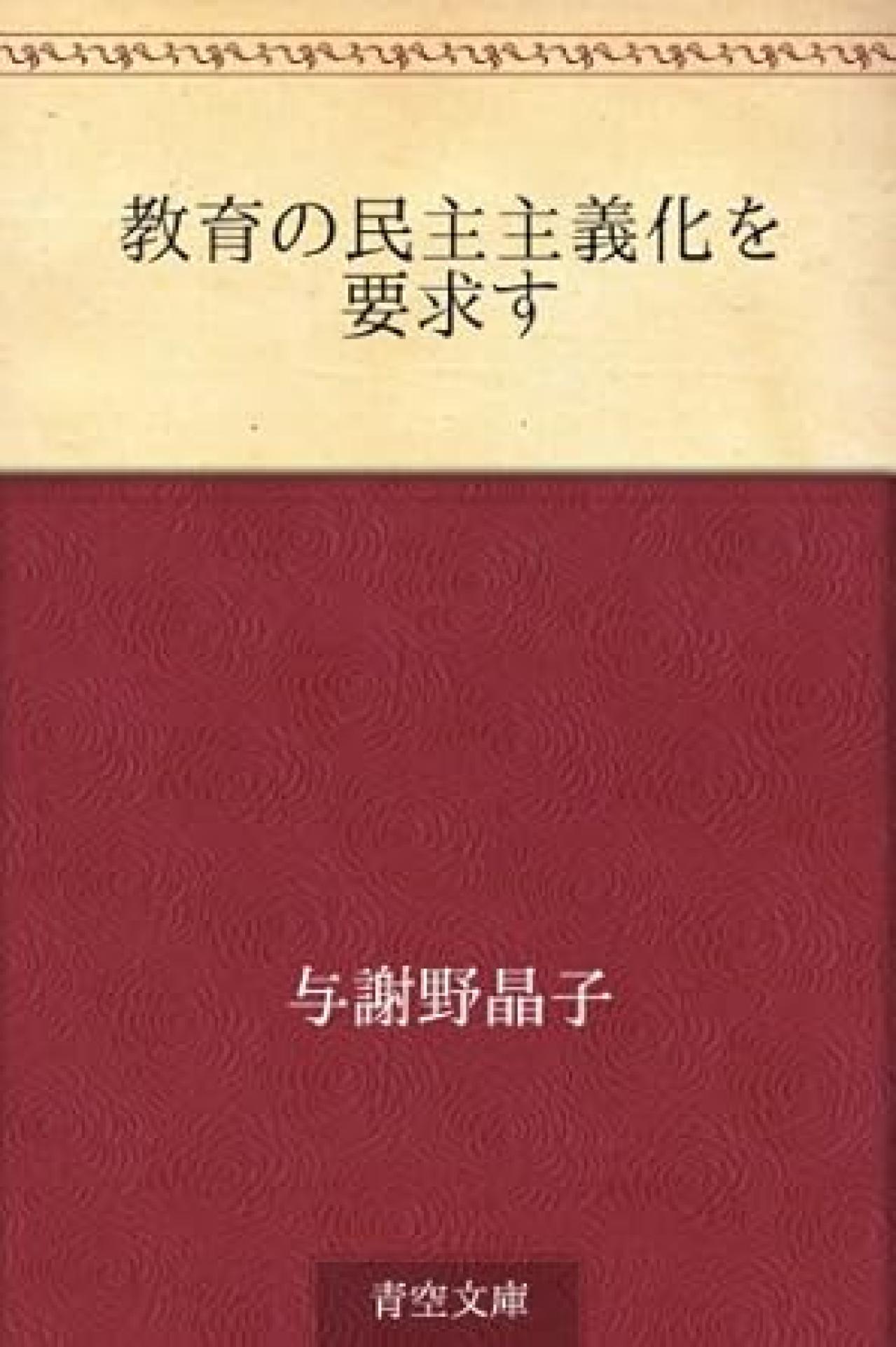
教育の民主主義化を要求す
与謝野晶子(著)
青空文庫(刊)
※詳細は以下のボタンへ






















