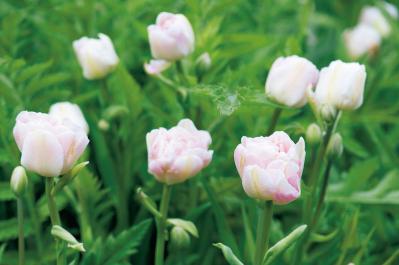【ガーデニング】初心者にもおすすめ 春の山野草10選と育て方【毎年咲く多年草】
公開日
更新日
光武俊子
みんな大好きな野の花【スミレ(菫)】
開花期:4~5月
草丈:約10㎝
日本中どこでも草地や道端に咲いているおなじみの花。仲間も多くて黄色の花を咲かせるキスミレもあります。初心者にも育てやすいものですが、寿命は2~3年と短いため、開花期のあとに出る花の咲かない閉鎖花からタネを取り出してまき、次の株を用意しましょう。
黄色の蜜腺と紫の雄しべが魅力【セツブンソウ(節分草)】
開花期:2~4月
草丈:10~20㎝
関東地方より西の本州に自生する、日本の固有種です。白い花弁に見える萼片をパッチリ開いてのぞく、黄色の蜜腺と紫の雄しべがチャーミング。節分のころに咲き出して晩春には地上部が消えるスプリング・エフェメラルで、夏は明るい日陰の涼しい場所で育てます。
ヨーロッパ原産のセツブンソウ【キバナセツブンソウ】
開花期:2~3月
草丈:5~10㎝
南ヨーロッパのアルプスに分布するセツブンソウの仲間。まだ黒々とした地面近くで咲く黄色の花は小さくても輝くような美しさで、遠くからでも目立ちます。本来は球根植物ですが、鉢植えの芽だし苗でも出回ります。夏は鉢ごと乾燥させ、秋に水やりを再開しましょう。
木陰を明るく軽やかに彩る イチリンソウ(一輪草)
開花期:4~5月
草丈:20~30㎝
本州~九州に自生して、人里近い山林などにも群生しています。よく似た花を2輪咲かせるニリンソウともども、初夏には地上の茎葉が枯れて休眠するスプリング・エフェメラル。ただ、花後に葉がすぐ枯れると翌年の花つきが悪いので、通風のよい明るい日陰に移動して葉を少しでも長く保ちましょう。
春に日差しを浴びて花開く【カタクリ(片栗)】
開花期:4月
草丈:10~20㎝
日本をふくむ北東アジアに分布。人里近い野山から亜高山帯の山地まで、日本各地で自生地が保護されています。ただ、分球しにくい球根植物でふやすことは難しいため、おすすめは黄花を咲かせる園芸種の‘パゴタ’。花は日差しがあるときだけ開き、花弁をそり返します。