【要約小説】名作のあらすじを読もう!
【戦後80年に読みたい小説】織田作之助の『大阪の憂鬱』あらすじ紹介。戦後の東京と大阪どう違った?闇市と残像が刻む戦後大阪の姿
公開日
更新日
ゆうゆうtime編集部
戦後80年である2025年に特に読みたい小説を紹介します。織田作之助のエッセイ『大阪の憂鬱(ゆううつ)』は、戦後混乱期の大阪を鋭い視点で描く文学的記録。闇市を舞台に、復興のたくましさと失われた情緒が交錯する姿が映し出されています。その中で生まれる哀愁とは?
▼他の要約小説も読む▼
>>【要約小説】名作のあらすじを読もう!小説特集憂鬱に包まれた大阪の現状
織田作之助は本作品の冒頭で、大阪を書くことそのものが憂鬱だと述べます。一方、東京のように作家たちの愛情に満ちあふれた土地と比較し、大阪は「実用的」になり果ててしまった実態を浮き彫りにします。戦後の闇市は、愉快さよりも混沌(こんとん)とした環境を形成しており、その中で描かれた大阪はかつて味わっていた魅力を失ったように感じると記します。
闇市に息づく人々の生活と矛盾
本作の中心となる闇市場の描写では、坂口の鋭い観察力と皮肉が際立ちます。「何でも売っている」という言葉に象徴される闇市場の実態は、驚きの連続。煙草の横流しや警戒の抜け穴を語る場面では、商品を巡る人々のたくましさと、警察の介入による混乱が同時に描かれます。しかし、それらは日常の一部として大阪の人々によって受け入れられており、日々の暮らしの中で特別な感情を引き起こすことはないのです。
美しき京都と対比される大阪
坂口は大阪からほど近い京都に滞在しながら作品をつづっています。焼け跡だらけの大阪と比較し、美しさを保つ京都の不思議さを指摘。そして大阪を「ややこしい」という一言で表現します。この言葉が大阪の複雑さと喪失感を的確に象徴していますが、それを正確に言い表すことすら容易ではない事実に坂口自身も翻弄されています。
復興と飽くなき渇望
著者は、大阪の復興のたくましさに言及しつつも、それは単なる飢餓感の産物ではないかと批判的に解釈します。かつてのにぎやかさを取り戻したかに見える千日前や心斎橋といった盛り場。しかし、それらは単なる悪あがきに過ぎず、失われた本質的な大阪の美しさを再現することはなかったと坂口は語ります。そして蛍が飛ぶ光景にだけ、わずかにかつての大阪の残像を見出しているのが印象的です。
まとめ
『大阪の憂鬱』は戦後の大阪を背景に、復興のたくましさとその裏に潜むはかなさを描いた織田作之助のエッセイ作品です。闇市場を中心に展開される物語では、混乱と欲望、そしてたくましさが奇妙に入り交じった社会が緻密に描写されています。また、美しい京都との対比を通して、大阪が持つ独自の魅力と哀愁が浮かび上がります。この作品は戦後日本の一面を切り取りながらも、良い意味での苦みと憂いを読者に提示しています。織田作之助特有の批評的な筆致で、まだ見ぬ大阪をご堪能ください。
▼関連書籍を読む▼
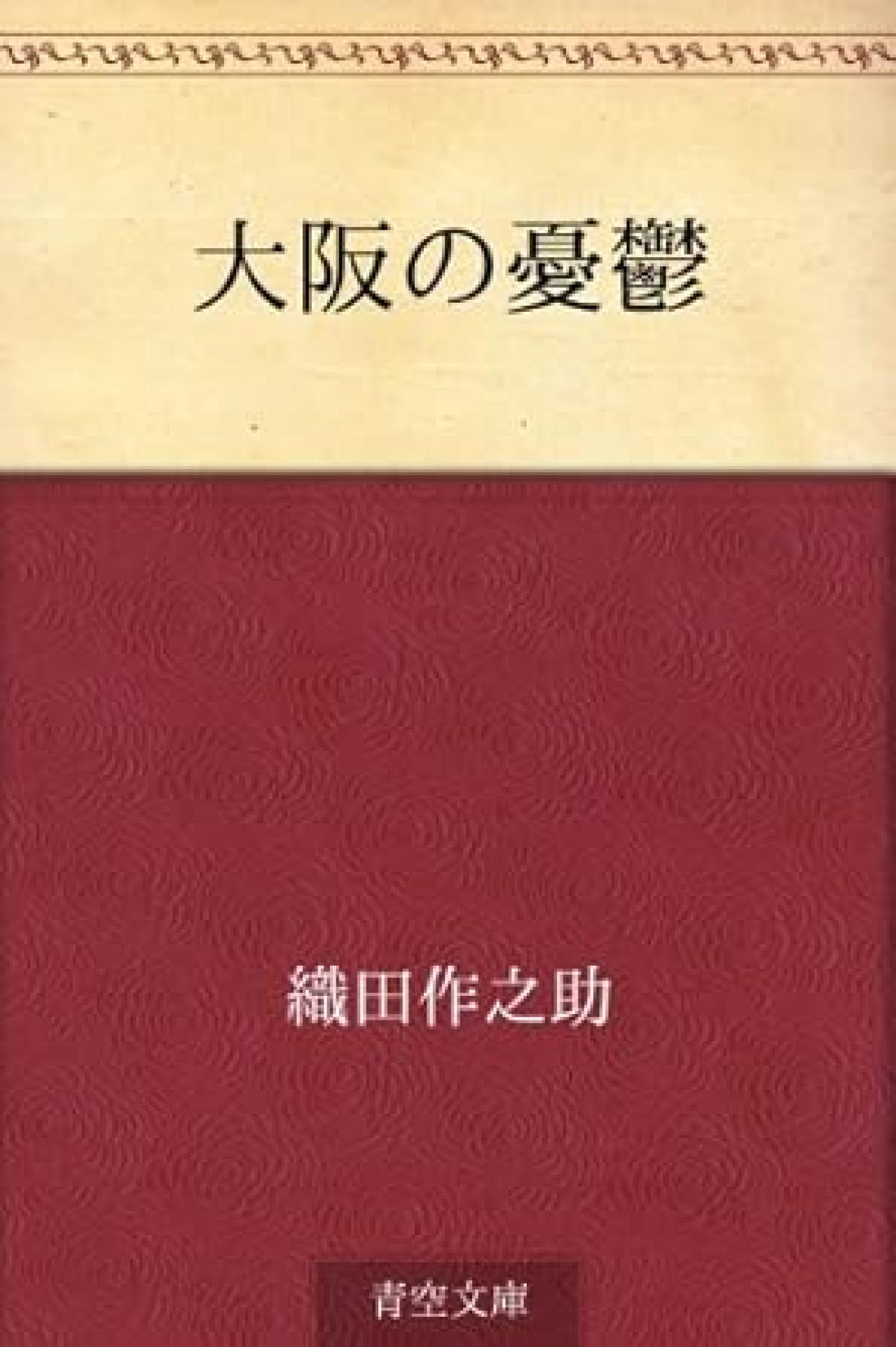
大阪の憂鬱
織田作之助(著)
青空文庫(刊)
※詳細は以下のボタンへ
▼あわせて読みたい▼
>>高村光太郎の『九代目団十郎の首』あらすじ紹介。団十郎の首の彫刻は完成するのか?大俳優を通してみる芸術の本質 >>【戦後80年に読みたい一作】岸田国士の『戦争と文化』あらすじ紹介。昭和を生きた作家の熱き思いと警鐘 >>石川啄木の『一利己主義者と友人との対話』あらすじ紹介。飄々とした会話形式で進む哲学的な物語※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。






















