50年前の刊行なのに【2025年上半期ベストセラー文庫1位】の快挙!有吉佐和子『青い壺』が共感の輪を広げる理由とは?
『青い壺』はなぜ、令和の時代に人々の心に響いたのか?
ちなみに有吉佐和子は1931(昭和6)年生まれで、いわば「ゆうゆうtime」読者の“母”世代。社会派の『恍惚の人』『複合汚染』、大河的な『紀ノ川』、『華岡青洲の妻』、伝統芸能の世界を描く『断弦』、エンターテインメントに振り切った『悪女について』など、多様な作品、ベストセラーを世に残し、1984(昭和54)年に53歳の若さで亡くなった。
復刊担当者の山口さんが「これはエンタメとして気合いが入った1冊だと感じました。初めて読んだときも、いまもそれは変わらない」と言う『青い壺』。この一大ブームを、没後40年の有吉さんは知る由もない。
では、『青い壺』はなぜ、令和の時代に人々の心に響いたのだろうか?
「着実に売れていた状態に火が付いたのは、書店でとてもよく動いていた『三千円の使いかた』の著者・原田ひ香さんが『青い壺』のことを褒めてくださっている記事を美容院にあった女性週刊誌で目にして、帯に推薦コメントをお願いしたことからです」(山口さん)
実は、『青い壺』には東寺の縁日で壺を3000円で売り買いするシーンが描かれる。「ほな三千円で、どないです」と言い放つ売り手。買い手の熟女が用意してきた金額は三十万円だった。
壺(モノ)が持つ価値と実社会の値段(お金の使い方)が織り成す葛藤や機微は、読者も自分ごととして小説『青い壺』に引き込まれる理由の一つなのかもしれない。
そして、ベストセラー作家・原田ひ香さんを引き寄せた青い壺の力は、プライスレス、だ。
▼後編に続きます▼
『青い壺』著者プロフィール
有吉佐和子(ありよし・さわこ)
昭和6(1931)年、和歌山生まれ。
昭和31(1956)年に『地唄』で文壇デビュー。
紀州を舞台にした『紀ノ川』『有田川』『日高川』三部作、世界初の全身麻酔手術を成功させた医者の嫁姑問題を描く『華岡青洲の妻』(女流文学賞)、老人介護問題に先鞭をつけ当時の流行語にもなった『恍惚の人』、公害問題を取り上げた『複合汚染』など意欲作を次々に発表し人気作家の地位を確固たるものにする。多彩かつ骨太、エンターテインメント性の高い傑作の数々を生み出した。
昭和59(1984)年8月逝去。
※本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです。
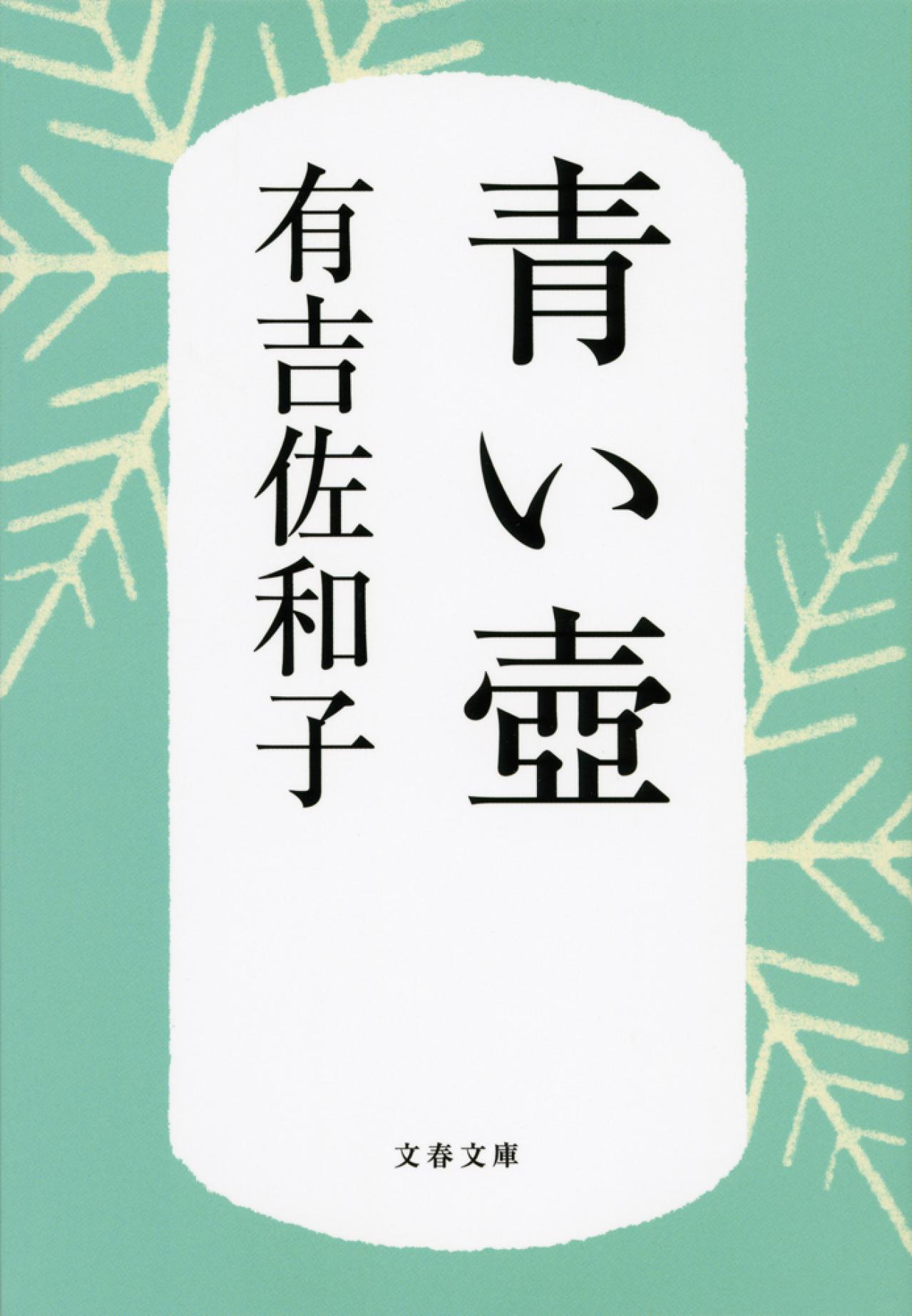
青い壺
有吉佐和子著
文春文庫
読めばハマる有吉佐和子。幻の名作長篇
無名の陶芸家が生んだ青磁の壺が売られ贈られ盗まれ、十余年後に作者と再会した時——。人生の数奇な断面を描き出す名作、復刊!
※詳細は以下のボタンへ
▼あわせて読みたい▼
>>『サン!シャイン』に毎日出演中!司会の谷原章介さんにかけられた思いもよらない言葉とは?【グラフィックファシリテーション山田夏子さんのターニングポイント#1】 >>「シングルで子どもがいない私」が、60歳目前で生まれ故郷・東京に戻ることにした理由 【広瀬裕子さんのターニングポイント#1】





















