【要約小説】名作のあらすじを読もう!
【戦後80年に読みたい一作】寺田寅彦の『戦争と気象学』あらすじ紹介。天候が歴史を動かす!?「気象学」が戦争に与える影響とは?
公開日
更新日
ゆうゆうtime編集部
戦後80年である2025年に特に読みたい小説を紹介します。戦争の勝敗を左右するのは、強大な軍事力だけではない!寺田寅彦が語る『戦争と気象学』は、気象がどれほど戦争を支配し、時に歴史までをも変えるのかを示す興味深いエッセイです。
目次
▼他の要約小説も読む▼
>>【要約小説】名作のあらすじを読もう!小説特集【気象が作る歴史—ウォータールーの雨と元軍の敗北】
冒頭で寺田寅彦は、ビクトル・ユーゴーが記したウォータールーの戦いの一節に触れます。1815年6月の大雨がナポレオンの計画に致命的な遅延を引き起こし、ヨーロッパの未来を変えたと。その例を引きながら、日本史における元寇(弘安四年)でも、暴風雨が元軍を打ち破った重要な要因だったと語ります。もし当時、元軍が現代のような気象学の知識を持っていたら、歴史は変わっていたかもしれないと示唆するのです。
【日露戦争や第一次世界大戦—気象学が戦争で果たした役割】
寺田は続けて日露戦争や第一次世界大戦における気象の影響を解説します。日本海での海戦では霧が、陸戦では満州の厳しい気候がわが軍の負担となった例を挙げます。また、第一次世界大戦では毒ガスや煙幕の使用の際に風向が重要視され、誤った予測が戦況に影響を及ぼしたエピソードを織り交ぜます。このように、気象が戦争の場面でどれだけ戦略的影響を持つかが詳細に語られています。
【気象学に疎かった英米と進んだドイツ】
一方で、ヨーロッパ諸国の気象学への対応の違いにも寺田は着目しています。ドイツでは早くから高層気象観測所が設けられ、カイゼル自らが支援を行ったのに対し、英国は気象観測事業を政府が扱うようになるまで時間がかかったと述べています。また、航空基地建設時の気象条件の軽視で多額の損失をかぶったイギリスのエピソードも紹介。これらの事例から、戦争において気象学の発展が一国の戦略に与える影響を強調しています。
【現代への示唆—シベリア出兵と未来の戦争】
さらに当時の時勢に触れ、日本がシベリア出兵を行う場合、気象学的知識の重要性を説いています。寒冷地での詳細な気象データが準備不足を防ぎ、戦争中の不測の事態を回避する鍵になると警鐘を鳴らします。また、大西洋を越える航空機輸送の計画など、気象学が未来の戦争に及ぼす影響についても鋭く言及しています。
まとめ
寺田寅彦の『戦争と気象学』は、戦争と科学(特に気象学)の関連性を鋭く描き出した文学的エッセイです。過去の戦争における天候の影響や各国の気象学への取り組み、また気象条件に基づく軍事行動の重要性が考察されています。この作品は、平和な現代においても「自然」を知らないことのリスクや科学の重要性を問いかけています。当時の時代背景を超え、現代の私たちにも多くのことを示唆してくれる一冊です。戦争をテーマにしながらも、自然科学の観点から世の中を俯瞰(ふかん)する視座は、日々の生活の中で忘れがちな「天気と人間の関わり」を再認識させてくれるはずです。
▼あわせて読みたい▼
※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。
▼関連書籍を読む▼
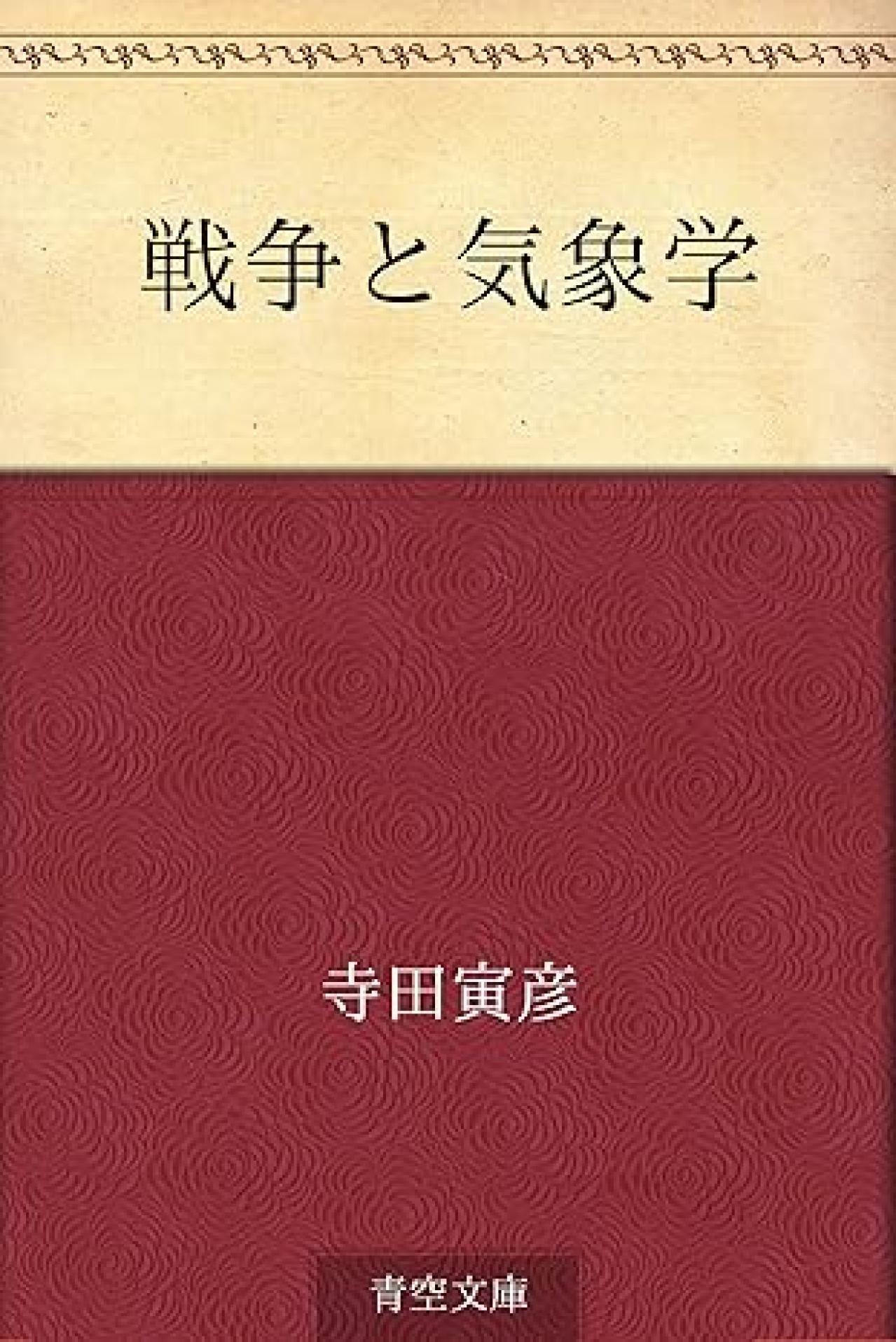
戦争と気象学
寺田寅彦(著)
青空文庫(刊)
※詳細は以下のボタンへ






















