【要約小説】名作のあらすじを読もう!
【戦後80年に読みたい小説】槇村浩の『出征』あらすじ紹介。詩に隠された戦争と革命の叫び
公開日
更新日
ゆうゆうtime編集部
戦後80年である2025年に特に読みたい小説を紹介します。槇村浩が描く『出征』は、戦争と革命を題材にした詩的な短編小説です。兵士として出発する主人公が抱える葛藤、希望、そして複雑な思いを現代に響く声として紡ぎ出しています。
▼他の要約小説も読む▼
>>【要約小説】名作のあらすじを読もう!小説特集戦争への出発と群衆の歓声
物語は電車が停まり、バスが斜めのまま停止した一瞬の情景から始まります。雪崩のような群衆の波、提灯や小旗で埋め尽くされた街並み。そしてその中で歓呼の声が怒涛のごとく押し寄せ、主人公たち兵士の心に何かを刻み込むようです。この「万歳」に包まれる空気の中、群衆の歓声が皮肉にも主人公の内面に疑念を生み出します。「本当にこの民衆の叫びは意義あるものなのか?」と。
「敵」とは誰か?はびこる葛藤
次に登場するのは、憤怒を交えた回想シーンです。主人公が軍隊内で拳を振り上げる連隊長から憎悪に満ちた敵意を叩きつけられる場面。敵視される「第十九路軍」について述べられる解説には、単なる軍隊以上のものとして働く彼らの側面が描かれます。それは中国プロレタリアートによる抵抗であり、抑圧への戦いでした。ここで初めて主人公の中に巣食う含みのある声が形になります。この敵への対応が正義と歩調を同じくしているのか、それとも権力の手駒になり果てているのかという問いが、主人公との間で鳴り止まない議論を誘発します。読者もまた、この問いにどのように答えるのか心の中で考えることになることでしょう。
仲間との連帯と兵士たちの心情
その後、場面は主人公の目から見た個々の兵士たちの姿に移ります。召集される立場の兵士たちはみな一様に蒼白な顔色をしており、意気揚々とは程遠い雰囲気です。そんな中「あざむかれた民衆」「よそおわれた感激」に囲まれる兵士たちの内面が一人ひとり浮かび上がります。眼鏡を曇らせる者や、女の共通話題へそらそうと不自然に笑う者、泣き濡れる者まで。そして背景には、出兵がもたらす破壊された田地や失業工場の影が差し込みます。
未来の誓いと共鳴する決意
物語の終盤、主人公は心に焦点を定めます。ただの出征兵ではいられないという決意です。「不平の声」に火をつける導火線となり、「軍隊」という外装をはぎ取る使命感。この誓いの場面では、革命に向けた思想が前面に押し出されています。本来的には抑圧や集団操縦の象徴とも言える軍隊、その内部で叛旗を翻す可能性を実感した主人公の姿がこそばされる重要場面といえます。
まとめ
『出征』は、ただの戦争文学を超え、革命の理想や抑圧との戦いを書き記した詩的物語です。群衆の歓声に包まれながらも違和感を抱く主人公の葛藤や、出兵する兵士たちの姿勢にリアリティーが満ちあふれています。さらに戦争そのものを新たな秩序を築く場と捉える視点が、多くの読者に新しい問いを投げかけます。槇村浩の大胆な問いと独特な詩的文体が読者の心を揺らし、読み手一人ひとりが「何に向けて声を上げるべきか」を考えるきっかけとなるでしょう。この作品は、単なる戦争文学でも、革命思想でもない、深い人間観察と未来への希望が籠もった一冊です。
▼あわせて読みたい▼
※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。
▼関連書籍を読む▼
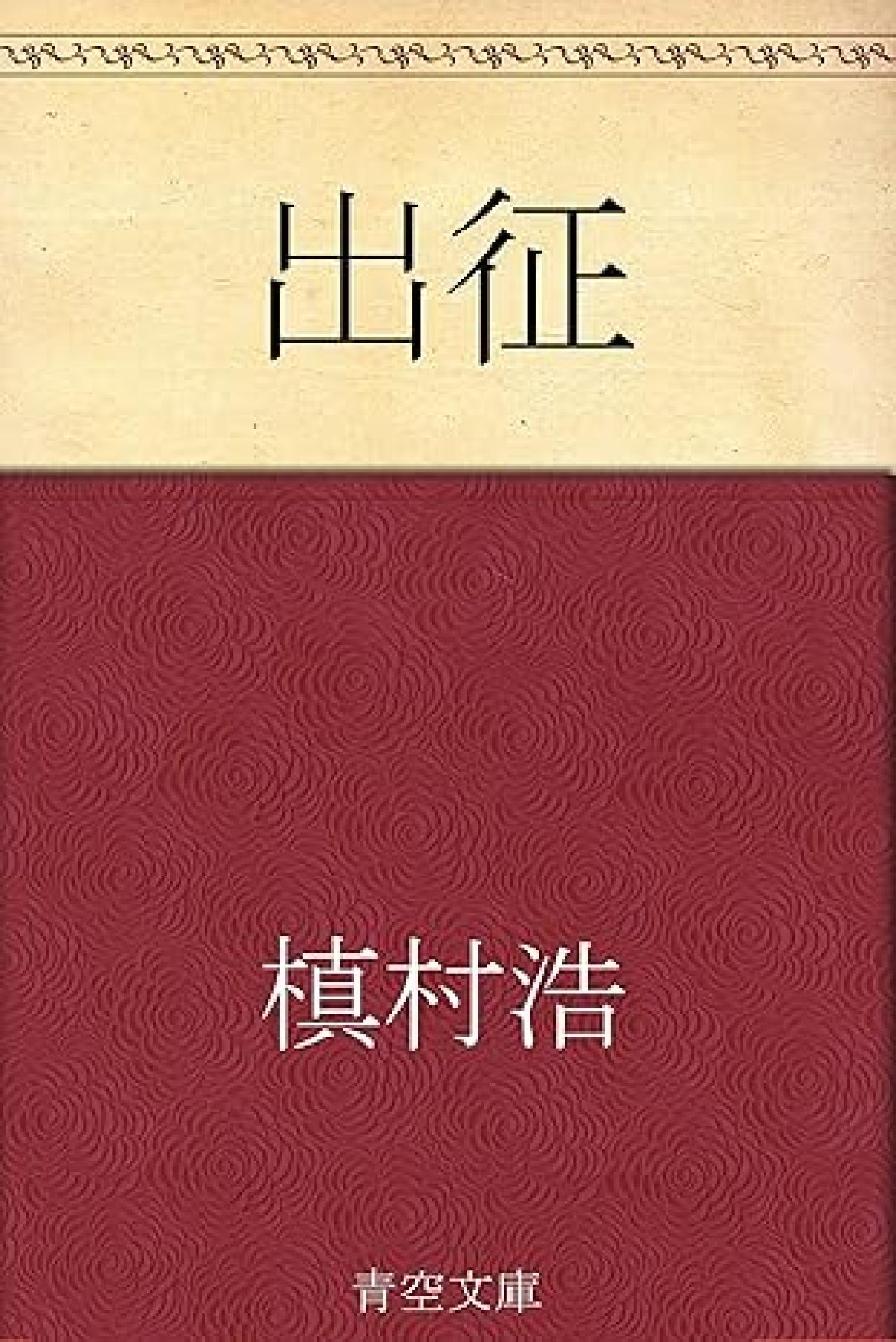
出征
槇村浩(著)
青空文庫(刊)
※詳細は以下のボタンへ






















