>>【要約小説】名作のあらすじを読もう!小説特集
二葉亭四迷の『余が言文一致の由来』あらすじ紹介。ことの始まりは「文章が書けなかった」から!?
公開日
更新日
ゆうゆうtime編集部
二葉亭四迷の『余が言文一致の由来』は、日本文学における大きな変革、「言文一致体」の始まりを語るエッセイ。この斬新な試みの裏には、挫折と工夫、そして情熱の物語がありました。さあ、日本語文体の進化の裏側をのぞいてみましょう。
▼他の要約小説も読む▼
>>【要約小説】名作のあらすじを読もう!小説特集坪内逍遥の助言と「東京弁」から始まる挑戦
二葉亭四迷が初めて「言文一致体」を書き始めた理由は何だったのでしょうか。それは意外にも、「文章が書けなかったから」というシンプルな動機でした。ある時、彼は坪内逍遥にどうすれば文章を書けるか相談しました。すると、坪内は「円朝の落語のように書いてみたらどうか」と助言。そこで、東京弁で実験的に書いてみると、坪内先生から「そのままでいい」という太鼓判をもらいました。
「私が~です」か「俺は~だ」か――どう表現するべきか?
言葉遣いの選択もまた重要なテーマでした。「です」調と「だ」調のどちらが良いのか。坪内逍遥の勧めで「だ」調を採用した二葉亭でしたが、山田美妙は逆に「です」調を選び、両者の流儀は分かれることに。この時期、2人の作風の違いは日本語の多様性を象徴しています。なんと興味深い対比でしょう。
俗語とポエチカルな表現のはざまで
二葉亭が追求したのは、言葉が「自然に発達した形」で使われることでした。彼は難解な漢語や古い表現を避け、現代的で生きた言葉を使うべきだと考えました。「べらぼうめ!」などの俗語を選んだのもそのためです。ただし、それは下品であると同時に詩的であるという特徴を持っていると彼は感じていました。平易で親しみやすい言葉の中に、どこか詩的な感覚を宿してみたい――そんな夢を描きながら、試行錯誤を繰り返しました。
美文の排斥とその後の彼
当初、二葉亭は坪内逍遥の「もっと美文に寄せたら」という助言にも背を向け、美文や漢文風を排除することにこだわりました。しかし、その結果は彼自身が「失敗だった」と振り返るほど苦しい挑戦でした。それでも彼は挑み続けました。今では再び坪内の考えに立ち返り、和文や漢文にも学びを深めていると語られています。何という粘り強さでしょうか。
まとめ
『余が言文一致の由来』は、日本文学史上重要な「言文一致体」が生まれるまでの道のりを、二葉亭四迷自身が語る貴重な作品です。文章が書けず苦労した彼が、生き生きとした「東京弁」に挑戦し、坪内逍遥の助言に従う中で、大胆にも文体改革を図ったのが始まりでした。しかし、その途中には「だ」調と「です」調の選択や、俗語利用の工夫、さらには美文拒否など、多くの葛藤や試行錯誤がありました。二葉亭の情熱と粘り強さは、現代の私たちにも挑戦する勇気を与えてくれます。このエッセイを通じて、日本語の進化にかかわる壮大なドラマを深く味わってみてください。
▼あわせて読みたい▼
※本記事の一部には自動生成による文章を含みますが、内容は編集者が確認・監修のうえで掲載しています。正確性には十分配慮していますが、最終的なご判断は公式情報等をご確認ください。
▼関連書籍を読む▼
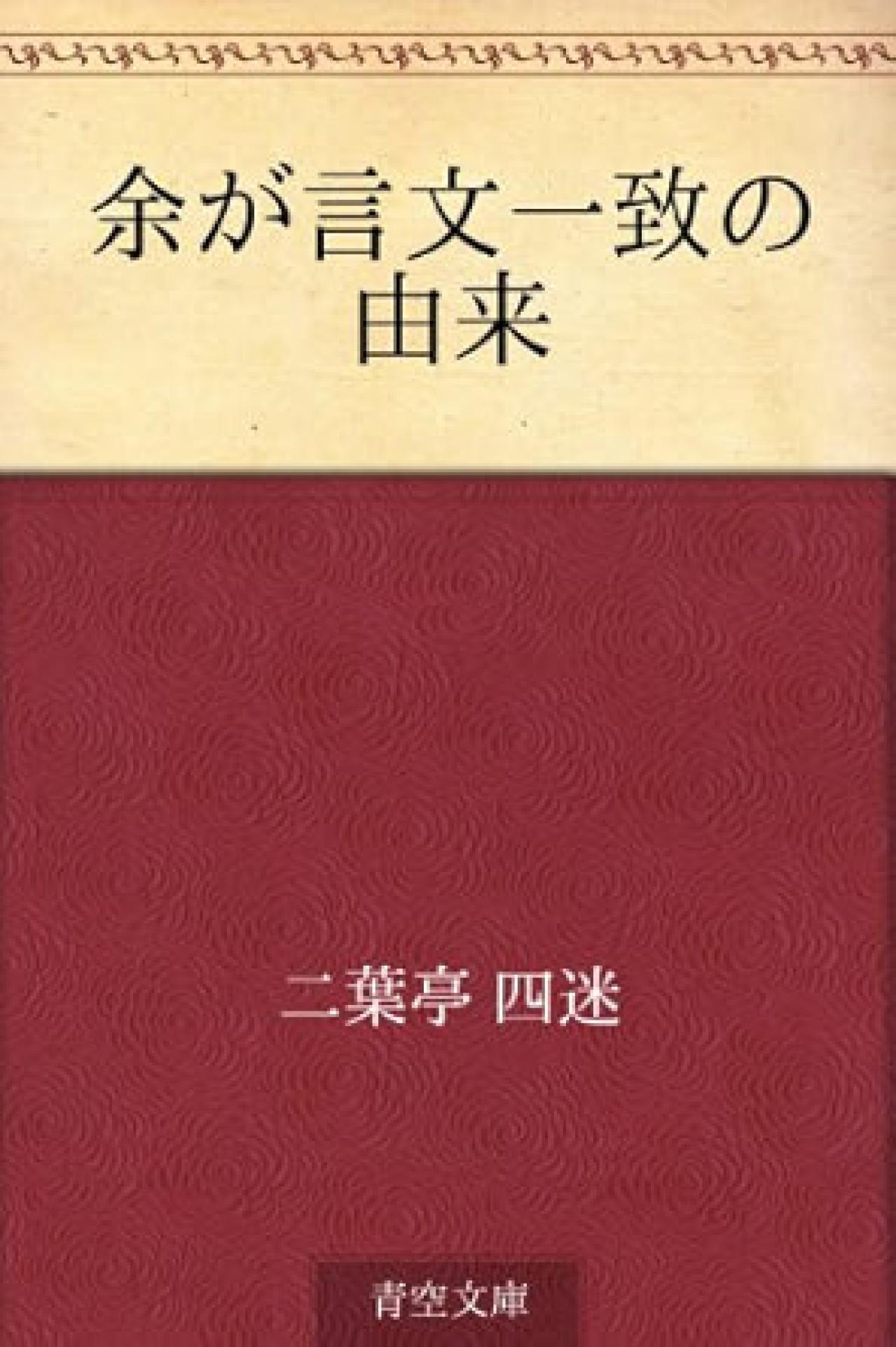
余が言文一致の由来
二葉亭四迷(著)
青空文庫(刊)
※詳細は以下のボタンへ






















