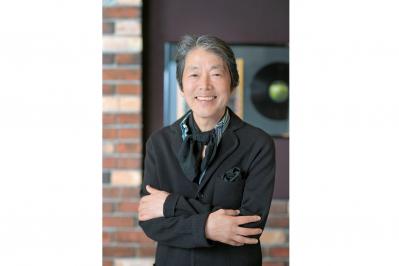【光る君へ】疫病にかかった紫式部(吉高由里子)を藤原道長(柄本佑)が看病するという“胸キュン” の展開に
公開日
更新日
志賀佳織
第16回のタイトルは「華の影」。都には疫病が蔓延してきて、いよいよそれは政権をも揺るがしていく事態となることが、なんとなく予感されていく。
登華殿は中宮の母・高階貴子が思い描いたような、才能豊かな若い青年たちが集う活気あふれるサロンとなった。年が明けたある日、雪が降った。定子が清少納言にこう尋ねる。「少納言、香炉峰(こうろほう)の雪はいかがであろうか」。すぐに我が意を得たりといった表情になった清少納言は、こう答えるのだった。「御簾(みす)を……。どうぞお近くで」
これは唐の詩人・白居易(はくきょい)が名勝・廬山(ろざん)を詠んだ一節「香炉峰の雪は簾(すだれ)を撥(かか)げて看る」を念頭においた定子の問いかけを、清少納言がみごとに受けた『枕草子』でも有名な場面の再現だ。互いに教養があって初めて成り立つやりとりで、その打てば響くような関係を楽しんだ間柄だったということがうかがえるエピソードだ。定子の表情がまたいい。「少納言、みごとであった」
一方、そんな長閑な光景が繰り広げられる内裏の外では、疫病が蔓延していた。しかし、道長からの度重なる進言も無視して、道隆の関心は、娘の定子が世継ぎを産んで自らの地位を全きものにする以外にない。
ある日、まひろが文字を教えていたたね(竹澤咲子)が訪ねてくる。熱のある両親が悲田院(ひでんいん)に薬草をもらいに行ったまま帰ってこないというのだ。たねに付き添ってまひろが悲田院に向かうと、そこは疫病患者で溢れていた。たねの両親はすでに亡くなり、間もなくたね自身も死んでしまう。
まひろは悲田院に残って、患者の世話をしていたが、そこへ道兼・道長兄弟も視察に訪れる。立ち働くまひろが振り返りざまにぶつかったのは、なんと道長だった。驚いて見つめ合う二人だったが、まひろも疫病に感染していて、そのまま道長の腕の中で倒れてしまう。
ここからの展開がこの回の絶対見逃せないクライマックスである。道長は、まひろを家まで送り届けるなり、看病を始めるのだ。ここはもう、少々古かろうが何だろうが(笑)「胸キュン」という表現以外にないだろうという場面だ。父である藤原為時(岸谷五朗)が、「大納言様にそんな……」と申し訳ながるところを「私のことはよい!」と叱りつけるさまも、ああ素敵すぎるじゃないか。
高熱に浮かされ意識のないまひろに、道長はたびたび話しかける。「久しいのう。なぜ、あそこに居た?」「生まれてきた意味は見つかったのか」。額を冷やし、首を冷やし、必死で看病する道長。しかしまひろの息は荒く、意識は戻らない。焦る道長がたまらず叫ぶ。「逝くな! 戻ってこい!」。道長、カッコよすぎるぞ!
必死の看病の甲斐あって、夜明けとともに、まひろの容態は峠を越したかに見えた。「あとは私どもで看病しますので」という為時の言葉に我に返り、現実に戻った道長は、帰ることにする。別れ際、そっとまひろの手に触れようとするも、ぐっと押し留めて立ち去る場面も切なかった。
朝方、屋敷に戻った道長を妻の源倫子(ともこ/黒木華)が出迎える。そして傍らに立つ女房・赤染衛門(あかぞめえもん/凰稀かなめ)にこう漏らすのだった。「殿の心には、私ではない、明子様(道長のもう一人の妻)でもない、もう一人の誰かがいるわ」。そう、いるの、いるのよ。何とかしてあげてと呼びかけたい気持ちだ。
離れたと思っても、何年も間があっても、巡り会ってしまうのがソウルメイト。これから互いがそれぞれの「生まれてきた意味」を探っていく中で、心の奥底では相手への思いを秘め続けていくのだろう。そして、この情熱がこれから、まひろを稀代の女流作家・紫式部へと導いていく。まひろもまた、書くことで悲しみを救われていくのだ。
★あわせて読みたい★











![【ザ・タイガース】旋風のその先に。別れの裏にあった、知られざる物語[79歳・瞳みのるさんのターニングポイント#2]](/images/articles/thumb20260115vs9fse202645835985.jpg)